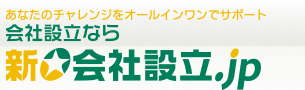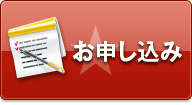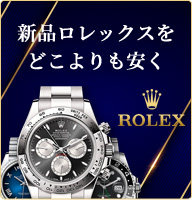2月や3月になると「決算セール」、「決算大売出し」といった販売キャンペーンを聞くことも多く、実際に利用されている方も多いのではないでしょうか。このキャンペーンは決算期を迎えるにあたり実施されるもので、実施する企業の経営者や担当者のみならず、購入する側の企業や消費者にも少なからぬ影響があるイベントです。
ここでは決算セールの目的・必要性やメリット・デメリットなどの特徴のほか、企業の決算期に実施される理由などを説明します。また、効果のある決算セールをおこなうための内容、計画の仕方などを紹介していきましょう。
1 決算セールは何故おこなう必要があるのか
決算期に「大売出し」などの決算セールが行われますが、なぜおこなう必要があるのか、しない場合にどんな問題や影響があるのかをここでは説明します。
1-1 決算セールによる売上予算の達成
その期の売上および利益の目標値を定めた予算計画を策定している企業では、その目標を達成するために決算月等において通常とは異なる販売キャンペーンとしての決算セールがよく見られます。
予算計画を達成し良い決算内容にすることが株主、資金提供などのステークホルダーから求められるため、企業の経営者は予算の達成を重視しています。そのため、決算期を迎えるにあたり経営者はそれまでの売上・利益の実績を把握し、それらが未達になりそうな場合経営者は対策を講じようとするわけです。
その対策の一つが決算セールで、未達の業績値の差を埋めるために良く実施されています。また、予算の達成も重要ですが、通期の業績が前年度実績を割り込みそうな場合決算セールはより重視されることになるのです。
前年度実績を下回ることは企業としてそれほど珍しいことではないですが、業界の伸びの動向と反して前年度実績にも及ばないとなれば、成長の鈍化や競争力の低下と評価される恐れもあります。そうした評価が株価の下落(上場企業)や融資の手控えといった資金調達等の運営上の問題に及ぶこともあるわけです。
こうした影響を未然に防ぐ、回避するためには前年度を上回る、予算を達成する売上が必要であり、未達になりそうな場合などで決算セールがその対策として活用されています。
1-2 決算セールによる在庫処分
長期在庫による汚損・破損した商品、陳腐化した商品などで翌期へと持ち越すことを回避するために、それらの商品在庫を決算セールで一掃する企業も少なくありません。
食品などは各商品に消費期限や賞味期限があり、その期間までに販売しないと廃棄の必要性が生じます。また、衣料や化粧品などのファッション関連商品では消費期限を有するもののほか、流行遅れにより販売のタイミングを逃しデッドストック化することもあるのです。
このように商品の中には一定期間以上に在庫することで廃棄やデッドストック、あるいは汚損や破損等で損失を被ることも少なくありません。そのため各企業は市場の動向を注視して適正在庫に努めていますが、それでも予想以上に在庫が多くなり売れ残ってしまうこともあります。
そのように損失に繋がりそうな在庫や必要以上に多い在庫を処分したい場合に決算セールが実施されるわけです。特に廃棄やデッドストックへ直ぐに繋がりそうな商品の販売は重要となるため、採算を度外視した赤字価格での販売も少なくありません。
破損・廃棄等により商品をまるまる損するよりも、多少原価を割ってでも販売したほうが損失は軽減されることになるため決算セールによる在庫処分がよく実施されるのです。
1-3 キャッシュフローの改善
予定以上の大幅な在庫でキャッシュ・アウト・フローが多くなり資金繰りが悪化することがありますが、余分な在庫を決算セールにより処分してキャッシュフローを改善することがあります。
決算業務が進む中でその期の利益額が予想できれば、翌期になってから支払う税額もおおよそ把握できるようになります。しかし、在庫が多くなり資金繰りが悪化している状況の中で税額が予想外に多くなれば、納税資金の確保も簡単ではなくなるのです。
また、期末に至るまでに仕入を多くしてしまうと翌期になってからの支払債務の手当てもしなくてはならないので、税金も含めるとさらに資金の確保は難しくなるでしょう。
期末でのキャッシュ量が十分でない場合、上記のような状態になってしまうとたちまち支払いに困窮することとなり、利息の高い短期の借入金を利用せざるを得なくなるかもしれません。
こうした事態を回避してキャッシュフローを改善するためには余分な仕入をしないことや余分な在庫を処分(販売)することが求められます。つまり、余分な在庫を一掃して資金を回収しキャッシュフローを改善するために決算セールが実施されることがあるのです。
在庫を少なくすれば売上原価はアップし利益は少なくなるので、税金も少なくなり、さらに資金繰りが楽になっていきます。
1-4 節税効果
決算セールにより期末在庫高を適切な範囲に調整することが可能なので、余分な税金の支出が抑えられます。
税金は企業が稼ぐ利益に課せられますが、その利益の大元は「売上高-売上原価」で求められます。つまり、売上原価が大きいと利益は小さく、売上原価が小さいと利益は大きくなり、税額はそれに対応することになるわけです。この関係でみれば、売上原価が小さいほど利益と税額は大きくなるので、企業としては売上原価を適正な範囲にコントロールすることも経営上重要になります。
その売上原価は「期首在庫+当期仕入高-期末在庫」で構成されるため期末在庫高の大小が利益および税額に直結し、期末在庫高が大→売上原価は小→利益は大→税金も大 となるわけです。
したがって、期末在庫高を少なくすれば、売上原価は多くなり利益が減り税金も少なくなる、ということになります。税額が多くなり過ぎるとその資金を調達するために少なからぬ手間とコストをかけざるを得ないケースも生じます。
そのような税金の負担や納税資金の確保の手間等を回避するために決算セールで期末在庫を調整することもあるわけです。
1-5 顧客への利益還元による囲い込みやライバルとの差別化
他の企業との販売促進における差別化や、顧客を囲い込み、新顧客の獲得ために決算セールが行われるケースもあります。
スーパーケットなどの最寄品を扱う店舗では、季節や祝日等の内容にあわせたイベントやキャンペーンを実施するケースが多いです。しかし、決算セールはそれらのイベント等とは若干性格が異なります。前者のイベント等では季節や祝日の内容に合わせた品揃えが強化され、目玉商品からプレミアム商品まで用意され関連商品と合わせた販売促進の実施が特徴といえるでしょう。
一方、決算セールでは超特価の目玉商品が用意されるものの品揃えに関しては平常時の販売とほとんど変わらないケースが少なくありません。つまり、決算セールでは平常時以上の値引きが主たる販促行為であり、儲けること以上に売り捌くことに重点が置かれて実施されるケースも少なくないのです。
また、通常よりも大幅に値下げした商品を提供して「日頃のご愛顧に対する感謝」や「顧客への利益の還元」をアピールする手段として決算セールが少なからず利用されています。
決算期だけの赤字覚悟の値引きは顧客にとっても魅力的であるため、その店舗に引き付けられ他社との差別化の戦術として利用されることもあるわけです。決算セールは既存顧客をファンとして囲い込み、今まで店舗を利用したことのない顧客に初めて購入してもらう、といった機会としても活用されています。
2 最寄品から生産財まで幅広く実施される決算セールの事例
ここでは決算セールが、いつ、どの企業や業種でどのように実施されているのかを具体的な事例から紹介しましょう。
2-1 決算セールの時期
決算セールは名前の通り決算期に実施されるので、決算セールを利用したい消費者にとっては各企業の決算期を知っておくことが重要です。一般的に決算セールは各企業の決算月中に実施されることが多いですが、その前後で行われるケースもみられます。
なお、企業によっては本決算のほか中間決算等でも実施されるケースがあるのでチェックしておくべきです。もちろん、決算月だからといって必ず実施されるとは限らないので、興味のある企業については事前にチェックしておきましょう。
①決算セールが多い月は?
一般的に決算月として多いのは3月と言われており、それにしたがうと決算セールは2月~3月頃に最も多く実施される可能性が高いです。
決算月の分布を日本取引所グループの上場企業数で確認すると、2018年3月末時点の上場企業数は3,607社で同年3月を決算月としている企業は2,166社、全体の約60%となっています。
また、国税庁の統計年報(平成27年度版)によると、年1回決算の企業の申告法人数は全体で2,632,784社であり、そのうち3月決算の企業数は508,030社で約19.3%となっています。なお、3月に次いで多いのは9月の287,241 社(約10.9%)で、2月は174,803社(約6.6%)です。
このように上場企業では約6割、法人企業全体では約2割の企業が3月を決算月としているので、3月およびその前後の時期に決算セールが多いと考えられます。
②スーパーマーケットやデパート等の小売業の決算月
スーパーマーケット、デパート、アパレルなどの小売業界では、本決算を2月としている企業が多いのが特徴です。それらの企業がすべて決算セールをしているとは限りませんが、第1章で確認した何らかの理由で急遽実施される可能性は十分あるため興味のある企業・店舗はその動向をチェックしておきましょう。
小売業界での2月決算が多い理由としてはいくつか考えられますが、8月とともに2月は個人消費が落ち込む閑散期である点が挙げられます。決算では会計処理の締め切りや棚卸作業など手間のかかる業務が多いため、多忙な時期を避けできるだけ暇な時期に実施される傾向があるのです。
小売業界においては、6月・12月はボーナス商戦、12月・1月は年越し・お正月商戦、6月・7月はサマー商戦などで売上も伸び忙しい時期となるので、比較的な暇な時期の2月が決算月に設定されやすいとみられています。
・ 2月を本決算月としている企業
| スーパー系 | イオン・ダイエー(イオン)、イトーヨーカドー、イズミヤ、アピタ・ピアゴ・ユニー(ユニー・ファミリーマートホールディングス)、平和堂、天満屋、マルエツ、西松屋、ベイシア など |
|---|---|
| デパート系 | 近鉄百貨店、東急ストア、東武ストア、松坂屋、三越、高島屋、大丸、西武・そごう、小田急百貨店 など |
| アパレル系 | しまむら、赤ちゃん本舗、オンワード樫山、東京スタイル、鈴丹、ジーンズメイト、タカキュー、西松屋チェーン、レナウン、など |
・3月を本決算月としている企業は以下の通りです。
名鉄百貨店(名古屋鉄道(株))、青山商事、はるやま商事
ほかにもアパレル業界はでは2月のほか、8月(ファーストリテイリング、ヤマトインターナショナル)、12月(三陽商会、ルックホールディングス)などもみられます。
③その他の業界
業界ごとに繁忙期や閑散期が異なるため、決算月も変わってきます。たとえば、各業界の繁忙期では次のような特徴がみられるのです。
不動産関係は12月~3月、運送業は3月~4月、自動車販売業は1月~3月、保険業は3月、ブライダル関連は4~6月や9~11月、ダイエット関連は6月~7月、飲料水・ビール等の販売業は7~9月が繁忙期といえるでしょう。
これらの繁忙期の後半や直後に決算月が設定され、その繁忙期の後半等に向けて決算セールが実施されるケースも少なくないです。
なお、自動車販売業では3月決算の企業も多いですが、2月から決算セールが実施されるケースが多くみられます。また、中間決算の9月に対しては8月頃に中間決算セールが行われることも少なくありません。
ただし、人気の車種によっては納車に時間がかかるため、決算セールの対象にならないケースもあるので注意しましょう。
2-2 決算セールの内容
ここでは企業が具体的にどのような決算セールをおこなっているかを実際の事例から紹介します。
①目玉商品・特別期間奉仕品
スーパーケットでは、食品・菓子類の広範囲の商品の中から奉仕品が設定され、特別価格などで販売されています。日配品、日用品や生鮮食品などの中にも対象とされる商品は少なくありません。
また、アパレルや家電などの業種でも特別価格を設定した決算セールが多くみられます。
A 業務スーパー(神戸物産)の決算セール事例(2016年10月22日~10月31日)
同社の決算セールでは、常に同社の売上上位にランクインする「ブラジル産鶏もも正肉」、野菜の価格高騰により注目を浴びている「冷凍野菜」、米や菓子など、いろいろの商品が目玉商品として決算セール価格で提供されていました。
| 商品 | 通常価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| ブラジル産 鶏もも正肉 2kg | 595円 | 495円 |
| 冷凍ブロッコリー 500g | 138円 | 118円 |
| 冷凍ポテト 1kg | 245円 | 225円 |
| 米10kg各種(一部対象外) | 通常価格から200円引き | |
| 米 5kg各種(一部対象外) | 通常価格から100円引き | |
(価格は全て税別)
B ビッグヴィジョン(オーダースーツ専門店)の事例
同社の決算セールの目玉商品は「決算在庫一掃2着セール」と題した2着による特別価格の提供です。
「春の気配が日に日に深まってくるこの頃、まだオーダースーツを試されたことがないなら、2着で39,800円(1着あたり19,900円)からと大変お買い得なこの機会にぜひお試しください。」
通常1着販売の価格が39,000円、2着で78,000円のスーツが、決算セールでは2着購入の場合に59,000円になるといった特別価格が設定されています。
このように2着での価格を大幅に値下げして決算セールでの目玉商品として、消費者の購入を促しています。また、販売方法でも親子、友人、職場の同僚などと各1着ずつでもOKといった購入しやすい方法も提供されているのです。
C ジョーシンWEBショップの大決算セール
ジョーシンWEBショップでは以下のような決算セールが開催されていました。
- 各種電気製品:タブレットPC、ハイレゾ対応ヘッドホン、ノートPCなど、週末限定で大奉仕(3月2日(金) 19:00 ~ 3月5日(月) 4:59まで)
- TVゲーム、おもちゃ、模型:1,000アイテム以上を決算大処分
- 音楽、映像ソフト:CD、Blu-rayやDVDソフトが10万タイトル以上22%OFF、アニメBlu-ray BOXが 40%OFF
なお、同社の実店舗では半期に1度ずつ決算セールが実施されており、特別価格の設定のほか、下取りによる大幅値下げ、無料の長期修理保証の提供といったサービスもあります。
②決算セールプレゼント
決算セールでは商品の値引き・特別価格の提供といったサービスのほかにプレゼンが実施されるケースもみられます。
D フェニックス(スーパーケット)
同社では以下のような決算セールでのプレゼントが実施されていました。
「2/16(火)~26(金)決算セール期間中の、当店お買い上げレシートをはがきに貼って応募していただいた方の中から抽選で、フェニックス全店合計で88名様に素敵な賞品プレゼント!」
A賞 ディズニーリゾートペアチケット 3組6名様
B賞 フェニックスお買い物券2,000円分 10名様
C賞 フェニックスお買い物券1,000円分 50名様
D賞 こしひかり米(2kg) 25名様
E アイオープラザ(アイ・オー・データ機器 PCおよび周辺機器の販売)
同社では「当店イチオシの省エネ液晶などを抽選で6名様に豪華プレゼント!」と題した決算セールプレゼントが提供されます(2018年6月8日~6月30日)。
期間中に応募した方の中から抽選で6名に、低消費電力パネルを採用した省エネ液晶ディスプレイのほか、テレビチューナー、ハードディスクなどのアイテムがプレゼントされるのです。
F クロカワ(車両販売、修理点検等)
同社の決算セールでは、軽自動車などに特別価格が設定されその上で新品タイヤ4本のプレゼンも用意されています。軽自動車の最安値では39.8万円という破格の値段設定の上に、タイヤやカーナビのプレゼントの提供も受けられるのです。
なお、期間は2018年6月6日(土)~6月8日(月)の3日間という短めの設定となっています。
③その他特典
価格やプレゼント以外にも顧客の購入を促すサービスが実施されています。
G イトーヨーカドー
イトーヨーカドーでは2018年2月15日~2月28日に決算セールが開催され目玉商品をはじめお得な商品多くみられました。また、同社ではネット販売でも決算セールが開催されましたが、ポイントサイト経由のポイント還元がこの決算セールでも適用されているのです。
「ポイントタウン」や「ちょびリッチ」などのポイントサイトのポイント還元率は1%が多いですが、「ハピタス」は2.4%と倍以上の設定になっています。決算セールをネットショッピングで活用したい方はこうしたポイント還元のサービスの違いも意識したほうがよいでしょう。
H 好日山荘(アウトドア品販売)
同社の2017年上期決算セールが4月21日~5月31日まで開催されました。セールでは最大50%offのお買い得品が多く用意されたほか、ポイント還元も提供されています。なお、WEBショップの場合のポイント還元は最大13%とお得です。
I SUV LAND(ネクステージ社 SUV車の販売等)
同社では2017年2月4日~12日の期間に決算セールが開催され、人気のSUVが超特価で提供されたほか、最大20万円の購入補助、ローンの利用による豪華グルメギフトプレゼントが提供されました。
④生産財を扱う企業の決算セール
最寄品といった消費財を扱う小売などの企業以外にも生産財を扱う企業でも決算セールは実施されているのです。
J ヤヨイ化学販売(糊・接着剤および関連機器の販売)
同社では特別価格品のほか、さまざまな決算セールでのサービスが行われています。
自動糊付機の下取りによる特価販売、指定テープの購入による「壁紙用ジョイント補強テープ」のプレゼント、サービス品のランダムな提供(特定商品の3ケース中1ケースの割合で提供)、パテ商品の購入品によるプレゼント(指定のはがきで応募)などです。
K 極東産機(畳・襖製造機器、業務用畳商品等の製造販売)
同社では2018年2月13日~3月30日まで決算セールが行われ、両框裁断機、返縫ロボットなどの高額機械が大幅値下げで提供されました。中には定価800万円の機械が400万円の半額設定で提供されています。ほかにも工具や薬剤なども特価で提供され、新畳の入れ替え、表替えなども対象となっておりその際には家具の無料移動サービスも提供されているのです。
3 決算セールの特徴のまとめ
ここでは今まで確認してきた決算セールの特徴をメリットやデメリットとしてまとめてみましょう。
3-1 決算セールのメリット
まずは決算セールを実施する企業側のメリットをまとめ、次は購入側のメリットを紹介します。
①実施する企業側のメリット
第1章の決算セールの必要性のところで確認してきた点をまとめると実施する企業のメリットは以下のような内容になります。
- 売上をアップさせ予算を達成させることができる
- 株主等が納得できる決算書の内容にすることができる
- 在庫を減少させることで売上原価を多くして利益を少なくし納税額が減らせる
- 在庫を減少させ長期在庫を防ぎ、破損等・陳腐化による損失が回避できる
- 他社との差別化や顧客の囲い込みが図れる
- 新規顧客の開拓や潜在需要の掘り起こしの機会にすることができる
②決算セールを利用する顧客側のメリット
利用する顧客には以下のようなメリットが得られるでしょう。
・通常よりはるかに安い価格で購入できる
決算セールでは目玉商品となる超特価の安値のほか、通常価格帯よりも安く買える製品が多く用意されるので、この期間中の買物は全般的にお得です。特に目玉商品には破格の値段が設定されることも多く、お気に入りの商品や買い替えで必要な商品などがあれば、絶好のショッピングの機会となるでしょう。
目玉商品以外でも通常価格より安く設定されるものも多いので、買い置きが可能なものをまとめ買いしておけばお得な買い物になるはずです。
・プレゼントや景品などがもらえる
企業によっては決算セールでさまざまなプレゼンを提供するところもあり、購入者は商品購入以外での経済的メリットが得られます。
第2章の事例にもありましたが、たとえば家電製品やお米などの商品、買物券、グルメ、旅行や観光スポットなどへの招待、購入品の関連商品(車ならタイヤ・カーナビ)といったプレンゼントです。購入品の関連商品の中には、「○万円分のオプション品をプレゼント」といった提供もみられます。
プレゼントには漏れなくもらえるモノと抽選でもらえるモノとに分かれますが、抽選の場合でも「あたるかもしれない!?」というワクワク感が期待できるでしょう。
・はじめての購買の機会となる
通常の高額な価格帯では購入意欲が湧かない商品でも決算セールでの大幅なプライスダウンにより初めて購入する意志が固まることもあります。
目玉商品などの超特価など、購入してもよいと思える価格帯に下がれば、購入の決断が促進されるわけです。また、「通常よりも○○円もお得!」という割安感やお得感が大きな満足感に繋がることもあるため、買ってみようという気持ちになりやすいでしょう。
3-2 決算セールでのデメリット
ここでも実施する企業側と購入側に分けて各々のデメリットを紹介します。
①実施する企業側のデメリット
以下のようなデメリットがあります。
・利益が大幅に減少し過ぎることもある
赤字を覚悟で破格の値段を設定した目玉商品の数量が少なくてもそれ以外の商品で価格を下げ過ぎると予想以上に利益が減少し、目標の利益を達成できなくなることもあるので注意が必要です。
目標とする売上だけでなく利益の総額も考慮して価格と販売数量を設定しないと、売上高は達成しても利益は未達ということになりかねません。赤字で売る商品の範囲を広げたり、わずかな利益しかない商品が増えたりすると、目標利益の達成は困難になります。
目玉商品の利益はマイナス○○万円、その他の特価品では利益はプラス□□万円、通常価格品での利益がプラス△△万円、といった決算セール全体での利益計画をしっかりたてましょう。
・顧客が決算セール価格に慣れて通常価格での売れ行きが悪くなる
決算セールを半期に1回、年4回実施している場合などでは、顧客はその価格帯になれてしまい平常時での通常価格の売上に影響することもあります。
特定の商品に対する超特価も繰り返し実施されれば、その価格にも驚きやお得感が和らぎ魅力も減退しかねません。そのように感じられるとその超特価での訴求力が低下して集客に結び付かない可能性も生じてくるわけです。
その結果、決算セールは不調に終わり、売上アップや在庫の削減といった目標を達成できなくなることもあります。そのため決算セールでの価格の設定、特価対象商品の選定や組み合わせによる販売といった販売方法を常に工夫することが求められるのです。
・一定のコストがかかる
決算セールを準備し実行するためには、実施・実現していくための人員や時間が必要であり、一定のコストが必要になります。
決算セールでは通常の販売時期とは大きく異なる価格設定を広範囲の商品対しておこなうことになります。また、在庫商品以外に決算セールように新たに仕入れる商品の手配も必要になるでしょう。加えて顧客への決算セールの告知、チラシの制作・配布のほか店内でのレイアウトや陳列方法の変更、POPの設置などが必要となる業種も少なくないはずです。
このように決算セールでは多くの業務があり、少なからぬ人員と時間を要することとなり、決算を迎える中で実施する社員にとっての負担は小さなものとはならないので注意しておく必要があります。
②購入側のデメリット
デメリットは以下のとおりです。
・型落ち品や流行遅れの商品を購入するケースも多い
決算セールで目玉商品となるタイプには型落ち品や流行遅れの商品などが対象になりやすいので、購入してからそのことに気付き後悔することがないように判断しましょう。
決算セールの対象品の中には処分してしまいたい型落ち品や流行遅れの商品も少なくありません。そうした処分用の商品は原価を割るような価格が設定されることもあり、購入側としてはその超特価は確かに魅力です。しかし、既に流行遅れになりつつあるような商品を買う羽目になるため、それを後で気付き購入を後悔してしまうこともあるのです。
最新の流行や機能などを気にしない方などなら問題はないでしょうが、流行遅れなどを気にされる方はその点をよくチェックしておかねばなりません。
・時期外れ品などは直ぐに利用できない、直ぐに利用できる期間が短いことも多い
決算セールの対象品の中には季節外れの商品、直ぐに利用時期が過ぎてしまう商品なども少なくないので注意が必要です。
例えば、2月の決算セールで冬物のコートを超特価で購入したが直ぐに着用できる期間が半月足らずというようなケースも生じます。また、消費期限が通常よりも短い商品を目玉商品としてまとめ買いした場合、結局消費期限までに全部利用できず廃棄するということも十分にあり得るのです。
安さに目が奪われ思い付きで買ってしまうと失敗することもあるので、購入後の使用を十分予測して購買することが求められます。
4 決算セールの進め方と注意点
今までの内容を踏まえ企業にとって適切で有効な決算セールを実施するための進め方を説明します。
4-1 決算セールの目的の明確化
第一に決算セールの目的を明確にすることが重要です。決算セールのやり方次第では余分なコストを費やすことにもなるので、定めた目的を達成させるだけでなく効率よく達成するためには、まず明確な目的の設定が必要となります。
既に確認してきた決算セールの必要性やメリットの内容から以下のような目的が挙げられますが、各企業は自社に最も適している点を設定(1つに絞る、あるは複数組み合わせて)しなければなりません。
- 予算の達成に向けた売上と利益の確保→決算内容の適正化
- 利益のコントロールによる節税
- キャッシュフローの健全化
- 在庫の健全化(長期在庫の抑制→汚損・破損・陳腐化・死蔵化の防止)
- 顧客への感謝→既存顧客との関係強化
- 新規顧客への誘導や獲得
4-2 決算セールの内容と予算
決算セールの目的達成に向けて必要かつ適切な内容を検討するとともに、実施した場合の売上・利益の目標額を設定し実現するための費用も見積もっておくことが求められます。
①売上・利益等の目標額の設定
予算の達成や節税などの関係から決算セールでどのくらいの売上と利益を見込むかを数値目標として設定するべきです。前節の目的を達成するためには具体的な目標が欠かせませんが、目的に合わせて売上高、利益額、期末在庫高、人件費や広告費等の経費、などを設定するとよいでしょう。
そして、その数値に基づいて決算セールの内容を検討していきます。
②決算セールの商品内容の検討
決算セールの内容はその目的や目標値に合わせて設定する必要がありますが、商品としては目玉商品、特価商品、通常価格品の3タイプに分けて売上と利益の計画を立案するのが重要です。
目玉商品は超特価の商品で赤字かほとんど利益がないような商品なので、販売個数の設定には特に注意しなければなりません。多く用意しすぎると利益を大きく圧迫することになりますが、少なすぎると訴求力の低下に繋がるためその適切なバランスの確保が求められます。
また、特価商品も目玉商品と同様にそのバランスの確保が重要ですが、目玉商品以上に対象商品が広範囲で量も多くなる可能性が高いことからより慎重な設定が必要です。決算セールは安さが訴求力となるので食品、日常品や嗜好品などから価格感応度の高い商品を選定することが重要になります。
そして、その対象となる商品の価格と販売見込量を設定し目標の利益を得られるように計画しましょう。もちろんの通常価格品の売上・利益についての予測を踏まえることが前提です。
③決算セールの期間の設定
決算セールの目的・目標を達成するために必要な適切な期間設定が求められます。
決算セールの期間を根拠もなく設定すると、目的・目標の達成が困難なるばかりか損失をもたらしかねないので注意が必要です。たとえば、期間が短すぎると目標を達成できず顧客からの不満が生じ、客離れの原因になる可能性があります。逆に長すぎると売上が達成しても利益を適切にコントロールできず、増え過ぎたり減り過ぎたりして納税額にも影響することになるでしょう。
他のバーゲンセールの期間の実績などを参考に適切な決算セール期間の設定が求められます。
④人員の確保と費用の見積り
決算セールは1週間以上といった比較的長い期間で実施されることも多く、そのため準備や運営には通常時期以上に人手がかかることも少なくありません。残業だけで対応できない場合には臨時のアルバイトの雇用などの準備も必要です。
また、そうした人員の確保や広告宣伝のための費用も必要となることから決算に向けて事前に予算化して費用を確保しておくことが求められます。決算セールの商品販売では目標の利益を確保しても運営面での費用がかかり過ぎ、結果的に目標の利益を大きく損なうことになれば意味がなくなります。そのため決算セールは運営面での費用もしっかり予算化した上で実施しましょう。
4-3 価格以外の訴求
決算セールの目的・目標を達成するためには価格面以外でのアピールも重要になります。
小売業などでは年間の行事・イベントを通じてさまざまなキャンペーンを実施しており、ありふれた値下げだけでは集客が困難になることもあります。そのためプレンゼント、旅行・演劇・グルメ等への招待・優待、ポイントの付与、下取り販売、送料無料といったサービスの併用も検討するべきです。
決算セールも顧客にとっては一つのイベントなので、価格面以外のワクワク感があるほど興味をそそり集客に繋がりやすくなります。どういった種類のサービスの提供が集客や売上に結び付くのかを過去の他のキャンペーンの実績をもとに新しいサービスを提供できるように工夫することも必要です。
なお、これらのサービスの実施も費用がかかるため計画内容の予算化が求められます。あまり大々的に実施しても多額の費用が必要となりますが、費用を抑えすぎると訴求力のないものになりかねないので注意しましょう。
4-4 決算セールのための広告
決算セールを成功させるためには広告が欠かせませんが、ここではどのように広告を実施するかを簡単に説明します。
①決算セール用の広告予算の設定
決算セールの目的・目標に合わせて広告費用の予算を計画すべきです。たとえば、チラシの配布のみで集客をおこなう場合は以下のような考え方でチラシの制作・配布の費用を予算化していきます。
第一にいくらの配布枚数で目標の集客ができるかを見積もることが重要です。チラシを不特定多数に配布した場合の集客率は良い業種の場合で0.1%~0.3%程度、食品スーパーなどでは1%と言われています。もっと低い業種では0.02%~0.03%とみられているケースもあるのです。
仮に食品スーパーで1%と見積もると、「チラシの配布枚数×0.01=集客数」となるので、1千人を集客したい場合は、「チラシの配布枚数=1千人÷0.01=10万枚となります。チラシの制作・配布の費用が1枚5円程度ならチラシの予算は、「10万枚×5円=50万円」となるわけです。
そのため決算セールの予算を検討する際には、この広告費を含めて決算セールおよび決算での目標利益(予算)を達成できるように計画しなければなりません。
なお、一般的なセールでは次のように広告費を検討します。
集客数を1千人、客単価を3千円、利益率を20%と設定する場合、1千人×3千円×0.2=60万円の利益が予想されます。このセールでの広告費を除く人件費等の経費が30万円とする場合、60万円-30万円=30万円が最大限広告費として利用できます。
先ほどの食品スーパーの場合なら1千人を集客するのに50万円のチラシ代が必要となるため、「50万円-30万円=20万円」のお金が不足することになるのです。そのため、予算の追加や他の広告手段との併用などの検討が必要になってきます。
②広告ミックス
チラシの予算が少ないため十分な量が配布できない、チラシだけでは広告効果が不十分だと想定される場合は他の広告手段・メディアの併用を検討しましょう。
たとえば食品スーパーで10万枚のチラシを配布するなら1千人の集客が見込めますが、他の業種なら10万枚×0.003=300人程度しか期待できないこともあるのです。そのためチラシだけでは1千人の集客は困難となるので、他の広告方法・メディアの活用も検討しなければなりません。
ホームページでの告知・広告、店内で告知・PR、メールでの個別案内などは当然必要です。高価格帯の耐久消費財や生産財などの業種では電話や訪問の際のPRなども欠かせないでしょう。
決算セールで利用できる広告費を考慮しつつ最大限効果が出せる広告手段を組み合わせて実行することが求められます。
③広告の準備期間
決算セール用のチラシを制作する場合、準備期間として2カ月ほどかかることもあるので、決算セールでの集客に効果がでるように早めに準備へ入れるようにしましょう。
決算セール全体の予算化、特価商品の選定、広告内容の設定(キャッチコピーやデザイン等)、チラシのラフの制作といった作業を経てチラシは制作されますが、約2カ月の時間がかかることもあります。何回も繰り返して実施していれば短縮も可能ですが、慣れていない場合は想定以上の時間が必要になることも少なくないので早めの準備が欠かせません。
4-5 価格設定での注意点
決算セールの目玉商品などで特別な低価格設定をしてしまうと、その影響が決算セール後にもおよび売上の低下に繋がるケースもあるので注意が必要です。
①ブランド価値を低下させない
通常高価格帯で販売されているブランド力の高い商品を通常価格の半額以下というような超特価で販売するとその商品のブランド力が低下し、高価格帯での販売が難しくなってしまうこともあります。
高級な材料により手間暇かけて高品質に作られているブランド力の高い商品でも一旦価格が大幅に下がると、その価格のイメージが強烈すぎてブランド価値は一気に低下することもあるのです。一度ブランド価値が下がれば以前の高価格では販売が伸びなくなることも少なくありません。
そのためブランド力の高い商品に超特価を設定する場合、包装に傷・汚れがある、型が古い、機能が最新式でない、といった理由をつけて販売することも必要です。
また、販売ではプレゼントとして提供するという方法もよいでしょう。決算セールで「A、B、Cの商品を○○万円以上買った方に高級ブランドのX商品をプレゼント」という方法も有効です。
②1個当たりの特価のイメージを定着させない
ブランド品以外でも価格を一旦下げてしまうと、その価格が消費者の購買基準となりやすいため、消費者にその特価として設定された低価格のイメージを植え付けさせないことが求められます。
たとえば通常300円で販売している商品を決算セールで200円にすると、その価格が購入基準になりかねません。これを回避するには、2個や3個といった複数個の販売で超特価を提示することが重要です。つまり、まとめ買いとなるので超特価になっているという理由をつけた販売にします。
「通常1個300円のもが3個で600円。300円もお得!」といった訴求の仕方で1個当たりの低価格イメージを残りにくいようにしましょう。
③個別商品で低価格イメージを持たせない
特定の商品だけを超特価にするとその商品を購入する上での価格水準が低下しやすくなるので、低価格のイメージを持たせない工夫が求められます。
たとえば他の商品と組み合わせて超特価にするという方法が有効です。通常価格が300円のA商品と500円のB商品を合わせて600円で販売するという方法になります。
こうすれば通常価格よりも200円安くなるので特価としてアピールでき、売上も大きくできるというメリットが得られるわけです。抱き合わせの販売なので各商品に対する低価格のイメージは持たれなくなるでしょう。