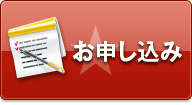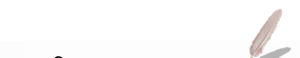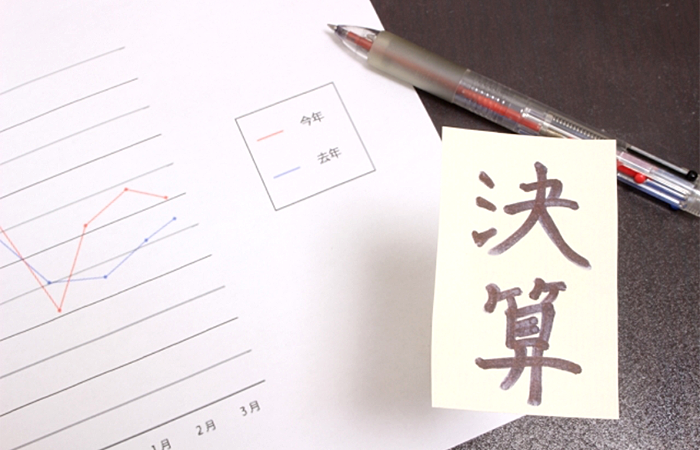
決算時期になり業務が大忙しという状態になって、「もっと早くから準備しておけばよかった!」などと後悔する経営者や経理関係者などは意外と多いのではないでしょうか。
決算は企業活動の1年を締めくくる重要なイベントですが、良い決算を迎えるためには適切な決算業務を遂行していく必要があります。ここでは決算業務の適切な処理の方法や経営上のメリットを得られる方法など、その望ましい姿を紹介しましょう。
1 決算業務を適切にする意義やメリット
決算業務は決算という行為を業務として実施する直接的な作業で経営上最も重要な業務の中の1つです。
1-1 決算業務の経営上の位置づけおよびその重要さ
決算業務は企業の1年の活動の集大成となる決算資料を作成し、適切な納税を行うための重要な作業です。そのため、経営者も社員も適切な決算を実施できるように決算業務に取り組まねばなりません。
①決算の目的
決算を簡単に表現すると、企業がその年度の事業活動で得た収入と、それに要した支出を計算しその結果である利益や損失を数字として発表する行為といえるでしょう。また、決算時には活動の成果以外にも企業が事業活動を行うために用意した資産・負債・資本の財務状況もまとめて発表しなければなりません。
これらは、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(・キャッシュフロー計算書)として作成され、株主総会に提出されることになります。また、証券取引所に上場している企業の場合は、取引所に提出しこれらを投資家に公表することが要請されているのです。
②決算資料の役割および用途
これらの資料はその企業の経営状況や財務状況を表すもので、例えるなら学生時代の成績表や健康診断の検診データのようなものといえるでしょう。決算資料を分析することにより経営状況の善し悪しが判断できるため、経営者は事業運営での改善などに役立てることができます。また、企業が公的機関等の補助金など各種の申請や届出を行うさいの提出資料として必要となることも珍しくありません。
ステークホルダーにとっても決算資料は重要です。例えば、投資家にとってそれらは貴重な投資判断材料となります。金融機関では彼らがその企業へ融資するさいの判断材料として利用されているのです。
このように決算資料は多方面で利用される貴重な資料なので、決算業務は極めて重要な役割を担っているといえるでしょう。
③税務申告に欠かせない業務
また、企業が1年間に稼いだ利益には税金がかかるため、決算業務では正確な税金の算定も必要です。誤った税金の申告を行うとペナルティーを受けることになるので日々の適切な経理処理だけでなく決算業務での正確な処理も求められます。
1-2 適切な決算業務を行うメリット
決算業務を適切に実施することで次のような6つのメリットが得られます。
| 1 | 税務申告のミスを防げる |
|---|---|
| 2 | 投資家や金融機関等の信頼が得られる |
| 3 | 経営上の適正な判断や経営力向上の土台になる |
| 4 | 倒産リスクを抑えられる |
| 5 | 節税対策がしやすい |
| 6 | 業務改善にむけた費用の削減が可能 |
①税務申告のミスを防ぐ
決算業務で適切に会計処理が実施され、適正な税金計算ができればその申告で過大納付や過少申告のようなミスが回避できます。
税務申告したあと、税務調査が実施されそのさいに申告内容のミスが発覚すれば、多額の追徴課税等の罰則が課されることもあります。日々の適切な経理処理に加え、余裕をもって決算業務に臨みルール通りに確実に処理していけばミスのない適正な税務申告は困難ではありません。
なお、税務申告に関する業務(会計処理や手続等)を全面的に税理士事務所などに依頼されるケースもありますが、税務申告にミスがあった場合罰則を受けるのは企業です。
そのため、税理士事務所等にすべて任せるのではなく、自社も税理士等と協力しながら適正な税務申告ができるように努めなければなりません。
②投資家や金融機関等の信頼を得る
決算業務を適切に実施すれば、それによって作成させる財務諸表といった決算書も適正化されステークホルダー(株主)の信頼を得る要因になります。
投資家や金融機関等は企業への資金提供の判断に決算書を利用するため、決算書が期限までに作成されることや、不備がない・疑義が生じえない適切な内容であることが必要です。もし粉飾決算しているかのような疑義が持たれたらステークホルダーからの信頼は消失してしまうでしょう。そのため適正な決算書は彼らとの信頼関係の構築・維持に欠かせないのです。
なお、不適切な決算書により投資家等が大きな損失を被った場合、損害賠償を求める訴訟に発展することもあります。逆に適正な決算書であれば、会計ルールに従って誠実に処理している企業として判断され一定の信頼に結び付くこともあるわけです。
③経営上の適正な判断や経営力向上の土台となる
経営者や管理職などは経営の判断等を決算の数字を根拠として行うことが多いため、適正な決算書を作成する決算業務はその判断の支えとなるわけです。
例えば、次年度の販売および利益計画、設備投資計画、採用計画などは前年度の決算の成績をもとに決定されるケースが多いでしょう。もし決算の数字が適切でなければ、上記の計画は誤った内容になってしまい計画と結果が大きく乖離する可能性が高まります。結果として、大きな損失を抱え経営危機へと進むことになるかもしれません。
逆に適正な決算内容であれば、事実に基づいた計画が作成できるため、計画と結果の乖離が少なくなり期待する利益の確保も実現しやすくなるでしょう。
適正な決算業務を推進していけば、月次決算の実施に行きつき毎月の経営状況の把握ができるようになります。年度初めの計画と月次決算の結果を対比すればその差異が簡単に把握できるため、改善の一手が打ちやすくなり計画も達成しやすくなるはずです。つまり、適正な決算業務を進めていくと経営の質の向上に結び付いていきます。
④倒産リスクを低減させられる
月次決算を行い期末の決算を適正に行えば、毎月の資金管理は向上していき、資金のショート等による倒産リスクを低減させることができます。
月次決算を行っていない場合、資金の流れが掴みにくく売上債権の管理も甘くなってしまいがちです。請求遅れや顧客のミスなどで多額の売上債権の回収が遅れれば資金が不足して倒産の危機に直面することになってしまいます。
また、年度の途中で人員を多数補充してしまうと給与だけでなく社会保険料も大幅に増加することとなり、キャッシュが不足して大慌てで調達に走るという事態になるかもしれません。
月次決算で毎月のキャッシュの流れを掴むようにすれば、こうした経営リスクは回避しやすくなるでしょう。
⑤節税対策もしやすくなる
月次決算も含めて決算業務を適切に実施していけば、費用として計上できる項目の計上漏れなどをなくし適正な費用計上による節税が期待できます。
決算ではその年度の収益を確定することになりますが、費用として計上できる或は計上すべき項目を計上しなければ結果として費用は少なくなります。その結果利益は多くなり税金も増えるわけです。
例えば、期末在庫高は費用科目である売上原価を算定する要素で、結果的に期末在庫高は利益と税金の額に大きく影響します。期末在庫の評価方法や在庫量の大小で売上原価を過小評価することになれば、利益は大きくなり税金も増加することになるのです。
また、少額資産購入の処理の仕方、決算前のプロモーション活動、社内旅行や決算賞与などの費用は利益を減少させ節税につながることもあります。詳しくは後述しますが、決算業務に余裕をもって取り組めば適正な費用を計上し適正な納税に結び付けることもそれほど困難ではありません。
⑥業務改善にむけた費用の削減も実現できる
月次決算をしている場合などは毎月の費用の把握が進み、無駄な費用の支出に気付きやすくなります。その結果、対策が打てるようになり業務を改善して費用の削減も実現しやすくなるわけです。
月次決算をせず、期末にあわただしく決算業務を進めてしまうと無駄な費用の大きさに気付くことも対策を打つこともできず、ただ計上するだけになってしまいます。こうした現象も単年度だけなら影響も小さいですが、何年も続くようなら企業の財務状況は悪化し経営危機へと陥ることにもなりかねません。
逆にもっと使うべき費用科目の支出の少なさに気付くのが遅れてしまうこともあるでしょう。売上げを大きくするには一定のプロモーション活動が不可欠ですが、日々の忙しさの中でやるべきプロモーションを怠ってしまうケースもあるはずです。そんな場合でも販売促進費の計上額の少ない点を月次決算で確認できれば、早めにプロモーション計画を立案し実行に移せるのではないでしょうか。
月次決算を含めて決算業務を適切に遂行すれば、無駄な費用を抑えるとともに使うべき費用の支出を促進しやすくなるので、業績の改善・拡大も期待できるでしょう。
2 適切な決算業務とは
ここでは適切な決算業務への取り組み方について説明します。
2-1 決算業務に取り組む手順
決算業務のおもな重要点の流れを簡単に紹介しておきましょう。なお、申告手続等は省きます。
・ 決算業務の流れ
| 1.早めの決算業務の計画とスタート | |
|---|---|
| ↓ | |
| 2.決算業務での重要点の実行 | おおよその利益額の算定 |
| その他の節税の検討と実施 | |
| 仮払金や仮受金などの仮勘定の整理 | |
| 不要資産の確認と処置 | |
| 預金などの残高証明書の手配 | |
| ↓ | |
| 3.決算日の作業 | 現金残高の確認 |
| 棚卸作業 | |
| 現物資産と固定資産台帳の確認 | |
①早めの決算業務の計画とスタート
決算業務を適切に遂行するためには時間の余裕をもってのぞむ必要があるため、早めに準備に入るほうが望ましいといえます。ただし、いつから始めるかについての決まりなどなく企業の事業規模などによって異なってくるでしょう。中小企業などの場合では決算日の1カ月以上前からやるべきことをリストアップし、それを確実に進めていくのが良いでしょう。
期末に近づくほど経営者や経理担当者は多忙を極めることになるのでできるだけ早めに決算業務を計画しスタートさせましょう。
②決算業務での重要点の実行
次のような内容の実施が求められます。
・おおよその利益額の算定
まず、どの程度の利益額になるかを経営者に提示しておく必要があります。経営者の予想に反して利益が多ければ、来期の売上げの拡大に向けた投資や福利厚生などに資金を充てることも可能です。納税額に影響するため早めの報告が重要になります。
・その他の節税の検討と実施
また、節税について検討し実行するべきです。その年度中に費用化すべきものをしっかり計上すれば、余分な税金支出を抑え適正な納税が実現できます。後述しますが、決算賞与の支給や少額資産の購入などを検討し実施するとよいでしょう。
・仮払金や仮受金などの仮勘定の整理
年度中にどの科目に該当するか判断に困り仮勘定で計上している場合、その項目がどんどん増えていき、期末に大慌てで処理するケースも珍しくないでしょう。早めに確認して正式な科目に引き当て、正確な収支が算定できるようにしなければなりません。
・不要資産の確認と処置
不要な資産がないか確認の上、それを廃棄或は売却し必要な資産を早めに手当てし行くと節税対策になる上に来期の業績拡大も期待できます。
事業活動に貢献していない不要資産は利益を生まないだけでなく、場合によっては事業活動の妨げになるケースも珍しくありません(例えば、工場の稼働していない機械は余分なスペースをとる)。また、固定資産を処分して除却損として計上すれば、実際にお金の支出がないにもかかわらず利益を減少させ節税につながります。
売却したり、除却したりすれば、キャッシュは増え、来期の業績拡大に貢献してくれる資産の導入もしやすくなるでしょう。
・預金などの残高証明書の手配
決算にあたり期末における預金や借入金の残高は把握しなければなりません。普通預金などは通帳を見れば確認できますが、当座預金については金融機関に残高証明を発行してもらう必要があります。早めに依頼して残高確認がスムーズにできるようにしましょう。
③決算日の作業
次のような作業が必要です。
・現金残高の確認
決算日の現金残高と現金出納帳の残高があっているか確認しておく必要があります。現金のチェックは税務調査時に行われるので要注意です。差異が生じて現金過不足が計上されている場合、原因が判明しないとしてもそのままにせず決算では雑収入や雑損失で処理するようにします。ただし、金額が大きい場合は税理士等に相談したほうが良いでしょう。
・棚卸作業
期末の棚卸作業は決算日における商品や製品・仕掛品の実際の在庫数量を確認する作業です。決算業務では期末在庫量を調べて在庫金額を把握し損益を確定させる必要があります。つまり、棚卸作業は企業の業績を確定させることにつながる重要な作業なのです。
早めに在庫量を含めて在庫状態を把握しておけば過不足のない適切は発注、不良資産の処分などが実施できるので、適正な期末在庫量および適正な利益の確保が可能になります。
・現物資産と固定資産台帳の確認
固定資産台帳にある資産が実際にあるか、またその金額が適正かを確認しましよう。台帳にないものが存在したり、台帳にあるものがなかったりするケースも少なくないので、廃棄や売却の有無などを含めしっかり確認しないといけません。
2-2 決算業務の成文化
経理規定に決算業務に関する規定を盛り込みやるべきことを明確にしておきましょう。
一般的には経理規定において決算業務の内容も含まれることが多いですが、決算業務の重要性の理解、適切な処理や作業の遂行を促すために、決算業務規程の作成は大きな意義があります。
決算業務での重要点や注意点を取り上げ明記しておけば、ミスを回避しやすくなります。その結果、適正な税務申告も可能となり追徴課税といったペナルティーを課せられる心配も少なくなるでしょう。また、適正な決算書の作成を実現し、それを株主や金融機関などへ公表できるようにすれば彼らとの信頼関係を良好に維持でき次期以降の経営も安定しやすくなります。
例えば、決算整理事項での注意点として以下のような点を挙げておくとよいでしょう。
- 資産の正確な把握とその適正な評価
- 負債の正確な把握およびその計上確認
- 未収金、前払金、未払金、前受金、貯蔵品の計上確認
- 減価償却費の適正な処理、計上漏れの確認
- 引当金の計上および戻入れの確認
- 積立金の積立額および取崩額の適正確認
- 注記情報の適正化および情報漏れの確認
- 決算数値の根拠を示す各種管理資料(明細表)の作成 など
3 決算業務の重要ポイント1~節税
決算業務の重要な使命の1つは過不足のない適正な税務申告を実現することですが、企業経営にとっては余分に支払う必要のない税金を削減することも重要です。日々の経理業務や決算業務の中で適切な処理を行えば節税を実現し次期以降の事業運営に役立つキャッシュの確保もしやすくなるでしょう。
ここでは決算業務で取り組むべき節税のポイントやその処理の方法を紹介します。
3-1 期末在庫の適正化と在庫方法
期末在庫は売上原価の算定に影響するため、安易に在庫量・在庫高を確定してしまうと利益の増大につながり納税額がアップしてしまいます。また、在庫を評価する方法も同様に納税額への影響は小さくありません。これらを適切に処理することが節税や企業としての適正な納税につながるのです。
①期末在庫の適正化
期末在庫量・在庫高を適切な値にすることで必要以上の税金の支出を抑えられます。
税金の算定に直接かかわる利益は「売上高-売上原価」の結果であり、売上原価が少なくなれば利益額は多くなり税金も多くなります。逆に売上原価が多くなれば利益は少なくなり税金も少なくなるわけです。
その売上原価は「期首在庫+当期仕入高-期末在庫」で示されることから期末在庫高の大小に影響されます。つまり、期末在庫高が多くなれば「売上原価は少なくなり→その結果利益は多くなり→最終的に税金が多くなる」わけです。
この関係から期末在庫高を少なくすれば、「売上原価は多くなる→利益が減る→税金も減る」ということになります。「儲かっていてキャッシュに余裕がありそうなので商品を多く買っておこう!」などと期末在庫高を増やしてしまうと税金を多く支払う羽目になりかねません。
逆に期末に販売価格を思い切って下げるといった「在庫一掃セール」などを行い期末在庫高が激減できれば納税額を抑えることができるでしょう。
また、長期間売れ行きの悪い商品、陳腐化した商品、破損品・汚れ品やデッドストックを転売、評価損計上や廃棄処分することも有効です。次期の販売に必要な在庫高を確保しつつ期末在庫高を適切に確保する管理は重要な決算業務の1つといえるでしょう。ただし、期末を迎えるぎりぎりの時期では適切な管理を行うのは困難なので早めに在庫状況を確認のうえ必要な管理行為に取り組まなければなりません。
なお、大量に廃棄する場合などは廃棄の証明やその事実を確認できる写真などを取っておくと税務調査のさいに役立つでしょう。
②見落としがちな未着品等
在庫が自社に属さない、あるいは自社以外の別の場所に管理されているような在庫のことを特殊在庫といいますが、発注して未だ自社に届かない商品等も未着品の1つです。
未着品が次期の期首に届いたとしても当期に発注し当期中に出荷された場合、当期の在庫として認識し計上することが求められます。つまり、期末在庫高が増え売上原価が下がり結果的に税金額が多くなるわけです。そのためこのような期末ぎりぎりの発注には特に注意しなければなりません。
なお、自社が発注した自社への未着品だけでなく、外注に支給した製品・部品や自社拠点間の転送品などの扱いにも注意したほうが良いでしょう。
③適正な在庫の評価方法
節税のために在庫の評価方法を決めるというのは適切とは言えないでしょうが、それでも一定の考慮はしておくべきです。
在庫の評価方法には大きくわけて原価法と低価法の2種類があり、原価法には6種類があります。各原価法と「各原価法と低価法の組み合わせ」の計12種類があり、そのうち1種類が選択できます。原則的には「最終仕入原価法」が使用さることになっていますが、届出により変更することも可能です。
もちろん何を選択するかは企業の自由ですが、一旦変更すると一定期間を経過しないと認定されないケースも生じるので注意が必要です。評価方法の選択は、その企業の業種・業態、経理処理の能力などにより決定されるべき行為なので、単なる節税目的の変更は推奨されるものではありません。
しかしながらその企業にマッチした評価方法により節税できることも十分あり得るので税理士等に助言を乞うとよいでしょう。
なお、実際には中小企業などを中心に多くの企業が最終仕入原価法を採用しています。各商品の期末に最も近い時期に取得した価格(最後の仕入単価)を評価価額とする最終仕入原価法は取り扱いが簡単なので、事務作業の負担も少なく済みます。
また、期中に高めの単価で仕入れていても最後の仕入単価が安ければ売上原価はそれで算定され、利益は少なくなり節税につながるわけです。こうした効果も期待できるので、検討の価値はあるでしょう。
*原則的に最終仕入原価法が適用されますが、「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出により、他の評価方法に変えられます。なお、評価方法の届出の期限や変更の期限があるので注意が必要です。
3-2 少額資産の減価償却
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に該当する取得価額が30万円未満の少額資産は全額損金に計上でき、節税に役立ちます。
この特例は、中小企業等が対象で平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得した30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できるという制度です。平成30年4月以降どうなるかは不明ですが、同様の特例が継続或は新設される可能性もないとは言えないので、注視しておく必要があります。
この特例では適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額の上限額は300万円です。対象資産としては、「器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産」に加え、「ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産」も含まれます。また、「所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産」も対象になると国税庁は示しています。
このように広範囲の資産が対象となっており、かつ合計金額300万円の設定なので利益が多く確保できている年度では有効な節税手段となるわけです。
3-3 不要資産の処分
すでに少しだけ取り上げましたが、ここでもう少し詳しく不要資産の処分およびその効果を説明します。
①節税効果
不要な固定資産などを廃棄し除却すれば、帳簿残高を固定資産除却損として計上できるので利益を圧縮することが可能です。この除却損はお金の支出のない損失なので税金が減る分だけ手元にキャッシュが残り経営に余裕を与えてくれます。
また、固定資産を除却するために費やした取り壊し費用なども除却損として計上できるので、利益が多くキャッシュに余裕があれば無駄で邪魔になるよう資産は除却するべきです。
さらに「解撤、破砕、廃棄等をしていない場合」でも除却損として損金計上できる「有姿除却」もあります。該当するケースは次の2点です。
- 「今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」
- 「特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの」
(出典:国税庁 法人税基本通達 第7章第7節第1款 除却損失等の損金算入)
このように有姿除却の場合は、解体撤去や廃棄等が不要であり、お金の支出を伴う費用をかける必要がないので、お金の余裕がない時などでは有効な節税になるはずです。
また、ソフトウェアについても「物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合」でも除却できます。先の国税庁の通達では、以下の2点がその除却の該当するケースとされています。
- 「自社利用のソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合、またはハードウェアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合」
- 「複写して販売するための原本となるソフトウェアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合」
経営の効率化や高度化を実現するために多くのソフトウェアが導入されるようになってきていますが、利用しなくなったものは事業経営には無価値です。利用しないソフトウェアを除却すれば節税につながるので早めにチェックして処理できるようにしましょう。
②業務の効率化
不要な固定資産を放置しておくと業務効率を下げる原因になる一方、逆にそれを処分することで業務効率を上げられることもあります。
製造業の設備・機械などでは稼働自体は可能であっても「生産性が悪い」、「製造する製品がなくなった」などの理由で使用していないケースもよく見られるでしょう。いつかまた使用するかもしれない、と考えてそのまま不要資産を放置している場合、それは製造現場の生産性を低下させる要因になりかねません。
広いスペースを取る設備などは工場の生産動線の非効率を招く要因になります。また、不要なものとして放置されるとその周辺に材料、仕掛品、工具・冶具などが置かれるようになり作業動線の大きさ妨げになることも珍しくないのです。
このように不要な資産があることで現場の業務に支障を来すこともあるので、その影響を十分考慮した処置が求められます。
3-4 決算賞与の支給
今期の利益が予想外に多い場合など、社員に決算賞与を支給すれば利益の圧縮につながり節税できます。ただし、実際に賞与としてキャッシュを支払うことになるので、キャッシュが不足している場合は注意して実行しなければなりません。
また、節税効果も高く一般的によく実行される手段でもあるので税務調査でのチェックは免れないでしょう。そのため、適正な決算賞与の処理と実行が求められます。
①決算賞与の税務上の特徴
それは未払いでも今期の損金に計上できる点です。期末におけるキャッシュに余裕がなく社員に決算賞与を実際に支給できなくても、一定の要件を満たせば決算賞与を今期の損金として計上できます。例えば、決算後1カ月以内であれば問題ありません。
決算業務が順調に進まず利益やキャッシュの概算の算定が期末のぎりぎりなってしまうと、決算賞与を支給する判断が遅れ結果的に支払いが困難になることもあり得ます。しかし、未払いでも計上だけ済ませておけばよいというなら期末ぎりぎりでの決算賞与の決断もできるようになるでしょう。
②節税効果でキャッシュの支出が軽減される
例えば、1,000万円の利益が見込める場合に400万円の決算賞与を支給した場合としない場合では以下のように税額に違いがみられます。
・決算賞与なしの場合
利益1,000万円×税率40%(仮定)=税金400万円
・決算賞与ありの場合
(利益1,000万円-決算賞与400万円)×税率40%(仮定)=税金240万円
この例では400万円-240万円=160万円の税金を減少させたことになります。つまり、決算賞与400万円のうち160万円を節税効果で補えるわけです。
③税務調査にあたっての注意点
決算賞与は税務調査での確認事項となりやすいので、適切な取り扱いが求められます。
・決算前に賞与を支払う
未払いであっても要件を満たすことで今期に計上できますが、税務調査で否認される可能性もあるので、できる限り決算前に支払うようにしましょう。
・書面で通知する
税務調査が入った場合に証拠を提示できるように、決算賞与の通知は口頭ではなく書面で行うべきです。
・できるだけ銀行振込で行う
社員への支払いについても証拠を残すようにしましょう。最善は銀行振込による支給ですが、現金払いのさいは領収書を受け取る必要があります。
3-5 従業員レクリエーション旅行の実施
従業員レクリエーション旅行、いわゆる社員旅行は一定の要件を満たせばそれに要した費用は非課税扱いになります。そのため実施していない企業が社員旅行を行えば節税につながるわけです。ただし、要件を満たさなければ参加した社員への給与として課税されることになります。
なお、社員旅行が国税庁の「所得税基本通達36-30」による以下の要件を満足している場合、原則として課税されません。
1 旅行の期間が4泊5日以内であること
なお、目的地が海外の場合、目的地での滞在日数が4泊5日以内であること
2 旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で実施する場合は、各事業所の従業員等)の50%以上であること
ただし、役員など特定の者だけを対象にすることや、不参加者に現金や商品券を支給することなどの場合は非課税にはなりません。また、旅行が社会通念上一般に行われている旅行とは認められない場合の旅行費用は課税されることになります。参考として国税庁の例を挙げておきましょう。
・以下の場合は非課税
旅行期間:4泊5日
費用および負担状況:旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
参加割合:100%
*旅行期間・参加割合の要件および少額不追及の趣旨のどちらも満足できると認められるので原則として非課税
・以下の用の場合は課税
旅行期間:5泊6日
費用および負担状況:旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
参加割合:50%
*旅行期間が5泊6日以上の旅行、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税
(出典:国税庁ホームページ タックスアンサー 特殊な給与 No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行)
3-6 来期に向けた広告宣伝
来期の売上拡大や新規事業推進に向けた広告宣伝などを決算までに行えば、来期の業績向上が期待できるとともに今期の納税額の削減にも役立ちます。ただし、十分な利益が確保できかつキャッシュに余裕があることが前提です。
来期から新製品を販売する、新たな事業分野に進出する、今まで進出したことのない地域に拠点を設置するなどの計画がある場合、それに向けた宣伝広告は重要になります。その事業目的に最も適切な時期に宣伝広告する必要がなければ、当期中に前倒しで実施するのも悪くないでしょう。逆に早めに実施しているほうが事業を推進するうえで高い効果が得られるケースもあります。
ただし、節税のためにあわてて宣伝広告を実施しても効果を得られなければ意味がないので、早めに計画し質の高い広告宣伝を行いましょう。
3-7 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)への加入等
経営セーフティ共済への掛け金は損金または必要経費に算入できるため節税効果が期待できます。
経営セーフティ共済は取引事業者が倒産した場合に、中小企業がその影響を受け倒産などの経営危機に陥ることを回避するための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)までの借り入れも可能で、毎月の掛金は5千円~20万円までで自由に選択できるほか増額や減額もできます。そのため未加入の方だけでなく既存の加入者も掛け金を増額することで節税に繋げられます。
支払った掛金は税法上、法人は損金、個人事業者は必要経費への算入が可能です。また、1年以内の前納掛金も支払った期の損金または必要経費に算入できます。なお、前納の期間が1年を超える場合、各事業年度末(決算期)において期間の経過に応じて必要経費もしくは損金の額として処理されます。
3-8 固定資産の修繕
所有する固定資産の維持管理や原状回復のために必要と認められる修理や改良等を行った場合、その支出したお金は修繕費としての損金算入が可能となるため節税に役立ちます。
ただし、修理・改良等により固定資産の使用可能期間が延長したり、その価値を増加させたりする場合、その延長・増加させる部分に関する金額は修繕費にならないので注意が必要です(資本的支出となる)。なお、修繕費にあたるかどうかの判定は修理・改良等の内容、その実質によって判定されます。
例えば、法令では以下のような支出は原則として修繕費に該当せず資本的支出と判定されます。
- 「建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額」
- 「用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額」
- 「機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額」
なお、上記の場合でも1つの修理や改良等の金額が20万円未満の場合や、約3年以内の期間を周期として行われる修理・改良等である場合、その支出したお金は修繕費として認められるのです。その認められるポイントをまとめると次のようになります。
- 通常の維持管理に必要である
- 破損した部分等の原状回復に必要である
- 約3年以内に1回は行われている
- 耐久性や価値は向上しない
なお、多額の費用が必要な修理・改良等の場合、修繕費として認められず資産計上することになるケースが多いですが、修繕費になるかは原則的にその実質的な内容で判定されます。そのため何百万円以上といった費用でも修繕費として認められることもあり、修繕費の扱いに詳しい経験豊富な税理士等に相談するとよいでしょう。
3-9 生命保険への加入等
法人契約で生命保険に支払った保険料は、その一部や全額が損金扱いになるケースもあるので該当する保険に加入および見直しをすれば節税効果が期待できます。
例えば、定期の生命保険の場合、国税庁の法人税法・基本通達・第3節保険料等では以下のように規定されているのです。
・定期保険に係る保険料(9-3-5)
法人自身が契約者となり、役員または使用人(その親族も含む)を被保険者とする定期保険*に加入してその保険料を支払った場合、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料は対象外)については、以下の区分に応じた取り扱いになります。
*「一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む」
1 死亡保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料は期間の経過に応じて損金として算入できる
2 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料は期間の経過に応じて損金として算入できる。ただし、役員または部課長その他特定の使用人(その者の親族を含む)だけを被保険者としている場合は、損金算入できずその保険料は、対象となった役員または使用人に対する給与となる
このように一定の要件を満たせば、法人契約で生命保険に支払った保険料を損金として処理できるので節税につながるわけです。
ほかにも定期付養老保険や、傷害特約等の特約の付いた養老保険、定期保険または定期付養老保険などの保険料も損金扱いとなるケースがあります。詳しくは生命保険に詳しい税理士や生命保険事業者などに相談してみましょう。
4 決算業務の重要ポイント2〜月次決算
月次決算は年次決算と異なり、会社法、金融商品取引法や法人税法などの法令に基づいて行われる業務ではないですが、年次決算および企業経営を円滑に行うための非常に重要な業務です。ここでは月次決算のおもな目的・メリットと実施するためのポイントを紹介します。
4-1 月次決算のおもな目的・メリット
月次決算は毎月行う簡易的な決算業務で、主に経営管理目的で実施される業務と考えてよいでしょう。表現を変えると年次決算書の代わりに月ベースの損益を把握するための月次試算表と各種管理資料を作成する決算業務といえるかもしれません。その月次決算を行う目的・メリットとして、おもに以下の内容が挙げられます。
目的1:計画の進捗度の把握
毎月の各事業や各製品での販売や生産などにおける計画と実績の差異が把握できるようになるため、未達のものに対する対策が早く打てるようになります。
目的2:赤字要因の分析
月次決算で毎月の損益が把握できますが、赤字や利益が少ない場合の要因を勘定科目から探し出すことも可能です。金額の多い費用科目のなかに原因が存在するケースは多いでしょうが、期間比較や業界平均比較などの分析をすると原因追求がさらに進むかもしれません。
目的3:年次決算業務の負担軽減(作業の容易化)
毎月の適切な帳簿整理、現金・預金の残高確認、仮勘定の処理、減価償却費等の計上、経過勘定の適切な処理などを実施しいけば、年次決算業務の負荷が軽減されます。
目的4:資金調達や投資等の計画の容易化
月次決算により経営計画の進捗度や収支が把握できるため、資金が不足する事態の予測も容易になり、資金調達に向けた対策が早めに実行できます。また、業績状況やキャッシュの過不足も的確に掴めるため、当期や次年度での設備投資などの計画も立案しやすくなるでしょう。
目的5:ステークホルダーからの月次決算資料の提出要請への対応
融資を受けている銀行等の金融機関から経営状況の説明資料が求められる場合、月次決算を行っておけば報告資料の作成が容易になります。また、月次決算を的確に実施していることをステークホルダーに示せば経営面での信頼度の向上につながることもあるでしょう。
4-2 月次決算を行うための注意すべきポイント
毎月の営業成績や財務状況を把握して経営管理の向上に役立てる月次決算の完了が遅ければ、その有効性は低下するため作業の迅速化が求められます。さまざまな考え方がありますが、月次決算の完了は毎月5日程度がベストといえるでしょう。
①月次決算はスピードが重要
業種・業態によっては10日でも比較的早いほうかもしれませんが、変化の激しい業界ではそれ以上遅くなると経営判断の遅れにつながることもあるので注意が必要です。
なお、月次決算は法令に従って行うものでないため、また経営管理目的でスピードが重視されるため、その作業は年次決算と比べ簡略化されても問題ありません。
ただし、スピードを優先するあまり正確さを欠いたり(簡易にし過ぎたり)、作成資料を少なくし過ぎたりすると、得られるメリットも減少するので注意しましょう。
②月次決算での留意点
月次決算を進めるにあたっては、以下の点に留意して経理処理等を適用させていくことが重要です。
・現金および預金の残高確認
企業の規模や業種などによりますが、現金は毎日照合し預金も定期的に記帳するようにして、月次決算では現金・預金の残高と帳簿残高を照合するようにします。実際の残高と帳簿残高とが合致しない場合は原因を確認の上修正処理をしておきましょう。
・売掛金、買掛金、その他経費
取引内容にもよりますが、売上げや仕入の計上は発生主義による計上が望ましいです。請求や支払いのタイミングやその他の観点で計上すると、毎月の決算データを的確に把握するのが難しくなる場合もあるので注意しなければなりません。
・月次棚卸の実施
月末に月次棚卸をするようにしましょう。ただし、在庫の種類や数量が多い場合は、一定のルールをもとに対象を限定とした実地棚卸や帳簿棚卸などで在庫金額を確定すると良いかもしれません。
・仮勘定の処理
仮払金や仮受金等の仮勘定は極力使用せず、使用した場合も月次決算で適正な科目に振り替えるようにしましょう。期末まで未処理でためておくと処理に余計な時間がかかりやすくなります。
・経過勘定の処理
事務所家賃等の前払費用や未払費用などの経過勘定科目は決算業務での決算整理仕訳で適切な処理が求められます。しかし、金額が少なく重要性が乏しい項目については経過勘定科目として処理しないことも可能です。経過勘定の決算整理仕訳は月次決算でもやや手間がかかるため、重要性の乏しい項目は税理士等に相談の上経過勘定として処理しないことも考えましょう。
・賞与、減価償却費、退職給付費用等の計上
毎期決まって発生する費用は、年間の金額を事前に見積もり月割りで等分して月次決算で計上するようにします。該当する費用としては、賞与(年2回)、減価償却費、退職給付費用、損害保険(年1回払い等)などの各種保険料、固定資産税や労働保険料などです。
・月次試算表の作成
月次決算業務を速やかに完了し、月次試算表を可能な限り早めに作成しましょう。会計ソフトなどを利用している場合、月次試算表の作成は容易で大した手間もかかりません。また、会計ソフトの中には試算表の期間比較や部門対比なども可能なタイプがあるので、導入のさいはそうした機能を考慮するとよいかもしれません。
・経営分析資料の作成
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書、損益分岐点分析、各月の売上高比較、生産性分析などその企業にとって重要な資料を月次会議までに迅速に作成しましょう。