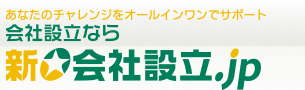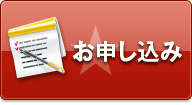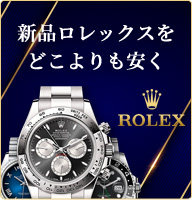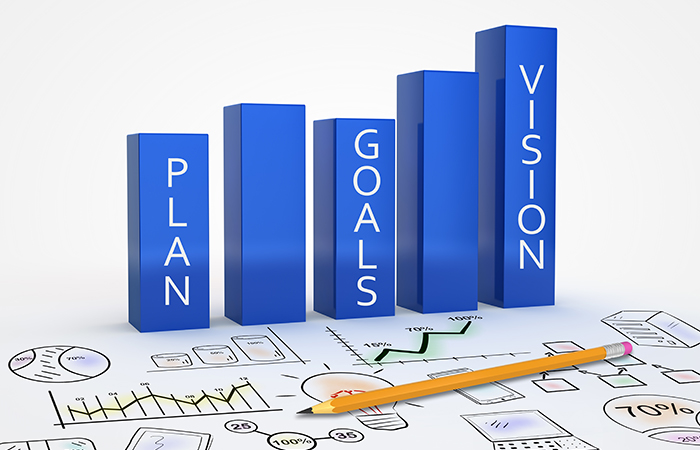
ビジネス、投資や就職・転職などで企業のことを調べる必要のある方などは対象先の経営戦略を分析するケースもあるはずですが、その際に決算資料は利用されているでしょうか。
決算資料は主に企業が1年間行ってきた活動結果についての報告書であり、企業がとってきた過去の戦略のみならず、今後の戦略についてもわかりやく端的にまとめてあります。
そのため決算情報を分析すれば、企業の戦略を把握でき今後の行動内容や業績を予想することも可能で、ビジネスのほか投資判断の材料としても確認利用されているのです。また、学生など就職先を検討している方などの研究材料にもなるでしょう。
ここでは決算情報から経営戦略の読み取り方を説明するとともにビジネスのほか、投資や就活に活用する方法などを紹介していきましょう。
1 決算資料(情報)の経営戦略情報を活用するメリット
自社の事業に関連する企業の決算資料から読み取った経営戦略の情報は、自社にとってはビジネス機会の発見に繋がるというメリットがあります。また、その戦略情報は、投資家には投資の判断、就活中の方には就職先候補の選定に役立つというメリットがあるのです。
1-1 ビジネスチャンスが探せる
自社の事業に関連する企業の決算情報を分析しその経営戦略が把握できれば、自社にとってのビジネスチャンスの存在を発見できるケースも少なくありません。
決算資料の有価証券報告書や決算説明会資料などにはその企業の経営戦略がわかりやすくまとめられており、自社にとっての事業機会になり得る情報がしばしば発見できるのです。
たとえば、食品加工機械の場合、食品製造業の決算情報に含まれる経営戦略や経営計画の中に自社の既存の仕事や新たな仕事に結び付く情報が少なからず存在します。
「A乳製品加工会社は今後ヨーグルト製品の製造販売に注力し、数年後までに設備を増強し現在の生産量および販売量を2倍にする」、といった情報が決算資料によく掲載されています。
上記の決算情報を確認したB食品加工機械会社がA乳製品加工会社と取引がなくても、A社は有望な新規取引の開拓先になる可能性があります。また、B社が既存の製品で対応できない場合でも、新製品開発の候補とし事業を拡大させる契機とすることもできるでしょう。
もちろん建屋などの施設、業務用の事務機器、配管や電気設備工事などの需要が期待され、ヨーグルト製品関連の原材料メーカーにとっても新たなビジネスチャンスになるはずです。ほかにも工場の増設にともなう従業員の補充などが計画されている場合は、人材紹介会社や人材派遣会社などにとってもビジネスチャンスとして期待できます。
経営戦略は目標の達成に向けて人、モノ、カネ、情報などの経営資源を揃えて具体的な活動へ展開するための指針です。そのため、決算資料の戦略情報からビジネスチャンスの情報を見出せるケースは少なくありません。
1-2 ライバル会社の戦略に備えられる
決算情報は自社にとっての事業機会を見つけるのに役立つほか、ライバル会社の戦略を把握して自社の競争優位性の確保に繋げるための重要な情報源にもなります。
自社の行動およびその結果の業績は、経済や法律などのマクロ環境だけでなく顧客(ニーズ)やライバル会社の影響を受けます。そのため企業としては、この3つの要素への適切な対応が求められますが、ライバル会社に対しては自社の競争優位を確保していくことが重要です。
競争優位を確保するには対象のライバル会社がどのような戦略を取るのかを把握しそれに対して自社が有利となる戦略を取らなければなりません。
たとえば、自社よりも事業規模が大きく資源が豊かな相手が低価格戦略で攻勢をかけようとしている場合に自社も同様の戦略を取ればジリ貧になることもあります。その場合には全面的な価格競争は回避し、性能・品質重視の中・高価格帯で差別化するという戦略の検討も必要となるでしょう。
こうした判断を下すためには他社の低価格戦略についてできるだけ正確な内容を掴む必要がありますが、それに他社の決算情報が活用できるのです。その低価格戦略で他社がどの程度の利益を確保できるのかなどを確認すれば、自社が価格で対抗できるかどうかの判断ができます。もしその手段の実行が困難であれば、価格以外の面での競争優位を確保して勝負するという選択になっていくでしょう。
逆に自社よりも事業規模が小さく資源にゆとりのない企業が差別化戦略で攻勢をかけてきた場合、その決算情報から戦略を分析し同じ戦略をとる同化戦略で優位を維持するという方法が考えられます。
このようにライバル会社の決算資料にある戦略情報は自社が対抗策を検討する上での基本情報となり得るのです。とくに決算情報の中でも決算説明会資料やアニュアルレポートなどで示される情報は長期の事業内容が詳しく掲載されるケースも少なくありません。そのため、それらの情報はライバル企業にとっては対抗策を考える上での絶好の作戦立案の材料となるでしょう。
1-3 将来性の期待できる投資先が検討できる
有価証券報告書は投資家保護を目的に作成が義務付けられている書類なので、投資家にとっては投資判断に欠かせない情報源ですが、その中の経営戦略に関する情報も投資の判断に役立ちます。
株価は企業業績の向上に伴う配当の増加や、それを含む企業価値の増大を見越して投資家等が市場で株式を売買した結果です。表現を変えると投資家等は多くのインカムゲインやキャピタルゲインが期待できる株式を購入するわけですが、端的には儲かりそうな企業や成長しそうな企業へ投資します。
そのためどう儲かりそうか、どう成長しそうかを示す経営戦略の内容は投資判断の材料として有益な情報となるのです。そして、決算情報の中にはその経営戦略の内容が分かりやすく説明している資料が多く用意されています。
たとえば、成長分野の業種に新規参入する、というような戦略は将来性が期待できるでしょう。決算情報にその戦略の内容として、予定の生産および販売時期、工場・設備等の生産能力に関する計画、開始から数年間等の生産量や販売量、などが示されているケースも少なくありません。
環境分析から戦略立案までの内容が妥当であり、計画の実現性も期待できる内容であれば、有望な投資先として評価できるはずです。逆に成長性や実現性に疑問が生じる戦略であれば、投資先として採用できないことになるでしょう。
投資の判断は財務諸表のデータにもとづく各種の株価分析やテクニカル分析などが重視されていますが、経営戦略の内容やその他のファンダメンタルの内容による評価も重要になります。
1-4 就職先・転職先の選定に役立つ
決算説明会資料などの決算情報はその企業の経営戦略の内容が分かりやすく示されているので、就活中の学生や転職を検討中の会社員の方などには就職先・転職先の選定材料として利用できるはずです。
就活中の学生の方などは就職先を検討する際に企業のWEBサイトや会社案内などで情報を入手して企業研究することが多いでしょうが、決算説明会資料も役に立ちます。
決算説明会資料は投資家や債権者などに自社が行ってきた活動結果や今後の活動などについてわかりやすく、かつアピールするために用意された資料です。つまり、それにはその企業が力を入れて行ってきたこと、今後力を入れていきたいことが端的に示されているのです。
そのため決算説明会資料は会社案内以上にその企業の特徴や将来性を把握しやすい材料といえます。
具体的な戦略内容が示されていることも多いので、成長性を判断できる以外にも就活者に適した業務が存在するのか、従事する機会が多いのか、などを予想できることもあるのです。
たとえば、生物科学等を専攻する学生の方などはバイオ事業を強化する企業などの決算説明会資料を研究すると就職先の選定に役立つでしょう。
その企業の決算説明会資料などにはバイオ事業等の戦略が分かりやすく説明されており、その内容からどのような人材が必要で、どのような働きが期待されているかを掴むことも可能です。
今後の生産量・販売額・投資額などの事業規模の情報のほか、新たな開発事業の内容や今後の補充人員の数、などが示されていることもあります。また、その事業が企業にとってのどのような存在、たとえば中核事業へ育成するといった情報が示されていることもあるのです。
社員としては今後企業の中核事業となる業務に従事することが出世に繋がりやすいため就活中にはチェックしておきたい点といえるのではないでしょうか。
2 決算資料からの経営戦略の読み取り方
ここでは、どの決算資料(情報)を見ればその企業の経営戦略の内容が掴みやすくなるか、といった点を説明します。
2-1 有価証券報告書で経営戦略を読み取る
有価証券報告書の中では第一部第2の【事業の状況】の1【経営方針、経営環境および対処すべき課題等】の部分が主に経営戦略等の説明になります。また、第一部第3の【設備の状況】は経営戦略を反映した投資計画が確認できるので有益な情報となるでしょう。
①【経営方針、経営環境および対処すべき課題等】の内容
この箇所では、まず経営方針が示され次に「中長期的な会社の経営戦略、経営環境および対処すべき課題等」が説明されるのが一般的です。
たとえば、森永乳業株式会社の2018年3月期の有価証券報告書の【経営方針、経営環境および対処すべき課題等】では以下のような内容が記されています。
- 平成28年3月期より平成32年3月期までの中期経営計画では、「成長に向けた事業ドメインの再構築」「資産効率の改善および合理化の推進」「経営基盤の強化」「社会への貢献」の4つが基本方針である。
- 事業ドメインの再構築は、「①機能性・食品素材事業の強化、②グローバル化の推進、③健康・栄養事業の育成、④既存事業の収益性の改善を将来に向けた事業」を4本の柱として推進している。
- 国内でのヨーグルト生産設備への投資、パキスタンでの育児用ミルクの製造・販売合弁会社の設立、米国でのヨーグルト事業展開といった事業強化策を実行および強化している。
- 「資産効率の改善および合理化の推進」に向けた全社的な生産拠点の再編として、利根工場に新棟の建設、神戸工場の製造ラインの増設。平成31年12月に近畿工場、平成33年3月に東京工場の生産中止、により効率的な生産体制の構築を目指している。
- 目標数値は、計画策定時点では平成32年3月期の連結数値目標が売上高6,400億円、営業利益が225億円だったものを営業利益については、1年前倒しの平成31年3月期の達成を目指す。
このような経営戦略(概要)が「国内の少子高齢化や人口の減少による市場の伸び悩み、お客さまのニーズの多様化」という経営環境に対応するための手段として設定されているのです。
厳しい経営環境の中で勝ち残っていくため事業の再構築を図ることが経営の基本方針とされています。そして、それを受けて具体的な戦略課題が策定され実現に向けた行動がとられるという点が上記の内容から確認できるのです。
②【事業等のリスク】の内容
【事業の状況】の中には【事業等のリスク】の項目があり、そこではリスク要因が記載されています。経営戦略を遂行する上で障害となり得るリスクをその企業がどう認識しているかが理解できる箇所ともいえるでしょう。そのため経営戦略を評価する際にはそのリスクについての確認も重要となるのです。
先の森永乳業の有価証券報告書で例を示すと、【事業等のリスク】の内容は以下のようになっています。
・酪農乳業界について
A 同社グループが生産する牛乳・乳製品には、WTO、TPP、FTA農業交渉の結果による関税制度の大幅変更となれば、同社グループの業績や財政状態に大きく影響する可能性がある。
B 同社グループが生産する乳製品の原料である生乳の生産者に対する加工原料乳生産者補給金制度が今後大幅に変更、廃止、補給金の水準が変化する場合は、同社グループの原料購入価格に影響が及ぶ可能性がある。
・食品の安全について
同社グループの製品製造にあたっては、製品の安全性や品質の確保に万全が期されるが、大規模な回収や製造物責任賠償に至る不測の製品事故などの発生により、業績および財政状態に重大な影響が出る可能性がある。
・ 相場/為替レートの影響について
同社グループは、一部の原材料および商品を海外から調達しているため、相場や為替レートの変動で購入価格が影響される。相場の高騰および為替レートの円安の進行は、原価が上昇し業績や財政状態に影響を及ぼす。
ほかにも「天候不順」「天災」「情報セキュリティ」もリスク要因として説明されています。
こうしたリスクに対してどのように事業で対応するのか、しているかという点について、その一部を有価証券報告書等の中で確認することが可能です。リスクとその対応という観点においてもその企業の経営戦略の実現可能性を評価するとよいでしょう。
③【設備の状況】の内容
【設備の状況】のうち【設備の新設、除却等の計画】は、経営戦略の中でモノの面から戦略課題を実現する具体的な手段と位置づけられ、その内容が計画として示されています。
【設備の新設、除却等の計画】では、その計画がある場合には「重要な設備の新設等」などの内容で掲載されることが多いです。内容としては該当事業年度末において、設備の新設、拡充、改修等の計画があるものの中で重要な案件が掲載されます。
たとえば、先の森永乳業の有価証券報告書では次のような内容(一部抜粋)が示されているのです。
| 会社名 事業所名 |
所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 資金調達方法 | 投資予定金額 | 着手および完了予定年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |||||
| 当社 利根工場 |
茨城県常総市 | 食品事業 | 新棟およびヨーグルト製造設備 | 自己資金 借入金等 | 21,740 | 491 | 平成28年9月 | 平成31年6月 |
| 当社 神戸工場 |
兵庫県神戸市灘区 | 食品事業 | 流動食製造設備 | 自己資金 借入金等 | 685 | 394 | 平成28年9月 | 平成30年9月 |
上記の2つの設備計画は、先に確認した戦略の内容に基づいて展開されている計画といえるでしょう。事業ドメインの再構築の「健康・栄養事業の育成」や「既存事業の収益性の改善を将来に向けた事業」の方針を具現化するための設備計画と判断できます。
とくに「国内でのヨーグルト生産設備への投資」や「資産効率の改善および合理化の推進」という戦略課題を実現するためのものといえるでしょう。つまり、上記の内容から森永乳業の経営戦略は「絵に描いた餅」ではなく、実際に実現さる見込みの高い計画となっているのです。
2-2 決算説明会資料で経営戦略を読み取る
決算説明会資料は、その企業が株主等にアピールしたい経営戦略等の重要点を端的にまとめた資料なので、有価証券報告書以上に理解しやすい情報となるでしょう。
決算説明会資料は有価証券報告書のように法令等に基づく提出書類ではなく決まった様式で作成・公開する必要もないことから企業の判断で好きなように作成し株主等へ情報提供できます。
そのため企業にとっては株主から支持が得られやすいポイントに重点を置いた説明ができますが、説明される側もその点が把握しやすいのです。さらに表やグラフなどが効果的に使用されると、業績や戦略の内容などの善し悪しが明確になりそれらに対する適切な評価が下しやすくなります。
なお、経営戦略等の内容を評価・分析するには以下のようなポイントを確認するとよいでしょう。
①決算概要
どの企業の決算説明会資料でも、まず当該事業年度の決算内容についての大まかな説明があり、どのような点を重視して経営してきたかが説明されるケースが多いです。
森永乳業の2018年3月期の決算説明会資料では最初に次のような内容で説明されています。
「取り組み・決算総括」 *評価として◎、○、△で判定
A 高コスト・低収益体質からの脱却
・原価アップへの対応、効率化と体質の強化
「製造コスト、販促費など、コスト
・経費の効率化への挑戦」 評価は⇒○
「2017年3月期実施の商品数削減効果の最適化」⇒◎
「価格改定の取り組み」⇒◎
B 持続的成長に向けた価値創造へのチャレンジ
・最高益更新に向けた取り組み、新たな100年へのスタート
「付加価値商品の更なる拡大」 評価は⇒△
「中長期志向での機能性素材の積極的なプロモーション活動」⇒○
「多様化するニーズへの対応(商品開発、マーケティング)」⇒△
上記の内容から当該事業年度の主要な戦略課題はAの「高コスト・低収益体質からの脱却」とBの「持続的成長に向けた価値創造」であることが理解できます。また、自己評価を見るとAのほうが達成度は高く、Bはあまり良い結果でないことがわかるはずです。
つまり、コストダウンなどの経営努力による費用構造の変革は進んだものの、成長に資する付加価値の創造という高度な事業活動はあまり進んでいないという結果といえるでしょう。それを示す具体的な内容が次の「2018年3月期業績」のシートで説明されています。
| 17年3月期 (単位:億円) |
18年3月期 | 対前年増減額 | 対前年増減率 | |
| 売上高 | 5,926 | 5,921 | △5 | △0.1% |
| 営業利益 | 211 | 217 | +6 | +2.8% |
| 経常利益 | 220 | 224 | +4 | +1.8% |
| 当期純利益 | 132 | 158 | +26 | +19.5% |
上表の通り、売上高は微減であるものの、営業利益以下の各利益段階で増額となっており、いずれも2期連続最高益更新が達成されていてその点が強調されていました。
最初の決算概要のAの評価のとおり、経営の効率化が実現されその努力が業績に表れた形でAの経営課題は合格レベルの結果になったといえます。しかし、売上高が減収であることは概要のBの評価を表したものといえ、今後の最重要課題としてその達成が急務となっているのです。
さらに以降のシートでは「事業分野別売上高、営業利益実績」についての説明があり、中期経営計画の4つの各事業の売上高、営業利益の実績が報告され、主要な事業の活動結果が確認できます。
②次期の業績見通し:経営環境、経営課題
株主や債権者などがより注目する次期(決算説明会の時には「今期」)の業績見通しについての説明が次のテーマとなるケースが多いです。
具体的な数値による業績見通しを発表する前に、どのような戦略をとり、何を経営課題として事業を進めるのかについての説明がよく行われます。
たとえば、森永乳業の場合では以下のような経営課題が立てられていました。
経営環境・経営課題
1 持続的成長に向けた価値創造へのチャレンジ
<次のステージに向け、成長を確固たるものへ>
・健康、栄養、機能性機軸の新商品の展開と定着
・国際事業の利益改善、事業拡大
2 あらゆるコストアップへの適切な対応
<原材料価格、チーズ向け原料乳価格ほか、人件費・輸送費等上昇(への対応)>
・継続的なローコストオペレーションによる成長投資余力の創出
・価格改定の取り組み(アイスクリーム、チーズ)、高付加価値商品へのシフト
3 環境変化への機敏な対応
<社内外の環境変化に対応した体制の再構築>
・チャネル変化に対応した商品開発、販売体制の整備
・最適な生産体制構築(近畿工場、東京工場生産中止)
同社の2019年3月期の経営課題としては、18年度で達成が不十分だった「持続的成長に向けた価値創造」が第一に取り上げられており、その重要性が確認できます。また、前年度では合格レベルの達成をみせた経営効率化にプラスしてコスト対応力の強化で高利益体質の基盤の強化やコストアップ要因への対応力強化の課題も設定されています。
加えて1と2の販売面やコスト面の課題を達成できるように開発、販売、生産の各体制の最適化が課題として設定されているのです。
このようにプレゼンテーション資料のシートには重要な戦略・課題の内容が端的に示されているので、有価証券報告書のような文章中心の説明よりもはるかに理解しやすいでしょう。
また、同社のプレゼンテーション資料のように説明内容入りのシートも用意されている場合、説明会に出席して説明を聞いている時と同じように事業内容等の把握が促進されるのです。
③中期計画の取り組み・進捗状況
そして、次年度(発表時点では今期)の経営課題の達成に向けた重点となる取り組み内容の説明があります。次年度の業績の達成はこの重点取り組み内容とその実行に左右されるため、この部分の内容は説明される株主や取引事業者等においても重要な評価材料となるはずです。
先の森永乳業の資料では、この部分については以下のように大きく3つに分けて説明されています。
2019年3月期
重点取り組みⅠ:国際事業の利益改善/事業拡大
・ミライ社事業の底打ち・反転
<安定稼働による赤字縮小、期中の黒字化目標>
・海外向け粉ミルク事業強化
<輸出および現地生産の取り組み拡大>
・米国ヨーグルト事業の深耕
<市場開拓中、現地ホールセールへの提案強化>
重点取り組みⅡ:付加価値商品の更なる拡大
・機能性ヨーグルト「森永プラスオン」ブランド
<「トリプルアタックヨーグルト」への集中投資>
・チルドカップ飲料
<「マウントレーニア カフェラッテ」発売25周年>
・BtoB事業
<乳代替品の提案、機能性素材の拡大>
・健康/栄養事業
<新市場の開拓>
など
重点取り組みⅢ:次の100年に向けた取り組み
最適な生産体制構築へ
・現在の当社グループの生産体制の最適化
<近畿工場、東京工場生産中止>
・食を通じた社会貢献の実現
<ビフィズス菌A1によるアルツハイマー病発症抑制>
・人財の活性化
<活力ある企業へ再加速>
など
以上の内容は当該箇所の一部を抜粋したものですが、重要ポイントが端的かつ網羅的に示されているので、経営戦略の中身を簡単かつ幅広く把握するのに適しています。決算説明会資料をベースとして、そのわかりにくい箇所などは有価証券報告書で確認していけば戦略の妥当性、有効性や実現可能性などが把握しやすくなるでしょう。
④中期計画の取り組み・進捗状況
最後に重要な確認事項として、継続している経営戦略や中期経営計画の取り組みおよび進捗状況について説明されることが多いです。
戦略や中期計画などは2~3年前に策定されているケースも多く、次年度はそれに若干の修正が加えられ継続されることが少なくありません。そのため、決算説明会時点では現在進行形で継続している戦略課題が結構残っているものです。
或は新年度になって直ぐに課題解決に向けた対策が実施されているケースもあるでしょう。これらの進行している戦略課題の取り組み状況等が説明会資料の最後のほうで説明されるケースが少なくないのです。
第三者が特定企業の戦略に関する妥当性や実現可能性を評価する場合、こうした進捗状況等のチェックが欠かせません。前年度から継続されている戦略課題にもかかわらず、進捗が芳しくないものは納得できる理由がない限りは実現困難との評価になることもあるでしょう。
2-3 財務諸表のデータで経営戦略の結果をみる
過去何年かの財務諸表のデータを比較することで、経営戦略の実行結果を確認しその実現の程度、有効性を数値面から評価できます。
中期経営計画や次年度の予算において業績目標が設定されているので、当該年度の財務諸表のデータがそれに達しているか否かで、戦略課題の実現の程度が判断できるはずです。
前節で確認したように決算説明会資料の中でも業績に関する説明があります。森永乳業の場合では営業利益などが2期連続最高益更新という情報が説明されていましたが、財務諸表のデータを期間比較すればそうした情報を自分でも把握できるのです。
また、決算説明会資料では説明されていない重要点を見出せることもあります。たとえば、下表の森永乳業の過去5年間の売上高と営業利益を見ると次のようなことが掴めるのです。
| 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | |
| 売上高 | 5,992 | 5,948 | 6,014 | 5,926 | 5,920 |
| 営業利益 | 119 | 68 | 143 | 210 | 216 |
(単位:億円)
この5年間の売上高はほぼ横ばい状態にあり、成長が停滞していると評価されても仕方のない状況といえます。営業利益は15年度に大きな落ち込みを見せ、16年度からV字回復し18年度は小幅な上昇となっているのです。
データだけを見れば、売上を伸ばすための戦略課題があったとしても実現されていない或いは実現したが効果がなかったということになります。営業利益に関しては15年度の大幅減額に対する対策が功を奏し16年度・17年度に急回復が実現され18年度にはその効果の限界が見え始めたと評価できるのです。
決算説明会資料では営業利益以下の各利益が増額で、いずれも2期連続最高益更新の点が強調されていましたが、売上高の停滞については詳しい説明があるとはいえません。
このように決算説明会資料や有価証券報告書の情報だけで分析していると、戦略上の重要点を見落としかねないので、財務諸表のデータによる分析も加えて戦略の効果を評価するべきです。
3 決算資料の経営戦略情報を活用する方法
決算資料の中で示されている経営戦略の情報がビジネス、投資や就活でどのように活用できるかについて説明します。
3-1 経営戦略の情報をビジネスに活かす
ビジネス面での活用としては、取引先相手として有望であるかどうかを経営戦略情報から判断するというものです。既存客先として今後の売上の増大が見込めるか、新規取引先として一定の需要が見込めるか、などの取引先相手を検討する際の判断に戦略情報の分析が役立ちます。
先に取り上げた森永乳業の経営戦略の情報からどのようにビジネス面で活用できるかを簡単に説明していきましょう。
①経営戦略情報から期待されるビジネスとは
決算説明会資料などで説明される経営戦略等の内容をビジネスに活用していく場合、どのようなビジネスの機会があるかを読み取ることが重要です。
森永乳業の2019年度の経営戦略の概要は、「持続的成長に向けた価値創造」「コストアップへの適切な対応」「環境変化への機敏な対応」という内容になっています。
これらの戦略上の経営課題を達成させるために、商品開発、販売および生産の体制を最適化することが主要な取り組み内容となっているのです。とくに既存製品の需要の伸びが期待できないため、健康・栄養・機能性といった面で新商品の開発および販売の強化が図られます。
また、コスト面での対応力の強化が図れることから生産面での体制の整備が進められるのです。こうした戦略情報からビジネスとして期待できる分野には販売チャネルや生産設備の提供などに関する事業が挙げられるでしょう。
販売チャネルとしては、既存の乳製品のチャネルのほか、今後は健康・栄養・機能食品分野のチャネル開発が重要となると考えられるため、その分野に強い商社などは有望なビジネス相手になり得ます。
今まで森永乳業と取引のなかった流通業者などでも健康・栄養・機能食品の取り扱いの実績などをアピールすれば取引はそれほど困難ではないでしょう。また、それらの分野で使用される原材料等を取り扱う事業者にとっては有望な新規顧客になる可能性も低くありません。
ほかにも健康・栄養・機能食品などを手掛けるベンチャー企業などは森永乳業との共同開発やOEM(相手先ブランドによる受託製造)といった業務を提案し新たなビジネスに繋げることも可能です。
生産面では生産の効率化や重点分野商品の製造強化などのために生産体制の再編が計画として実行されつつあります。新棟の建設や各種設備の導入が進められているので、関連する建設企業や設備製造事業者にとって同社は有望な顧客になるはずです。
このように決算情報の経営戦略の内容からその企業がビジネス相手になり得るかが判断できるでしょう。
②設備投資の計画はビジネスに直結する
戦略遂行上の課題として設備の増強が謳われているケースでは建設・設備・情報システム等の事業者にとってはビジネスチャンスになりやすいはずです。
たとえば、設備計画の内容によっては以下のような内容の事業機会が期待されます。
A 工場や事務所の建設や設置
建屋の建設工事、電気工事や配管工事のほか、事務機器や事務什器・家具、給湯設備、トイレ設備、空調設備等の需要が期待できます。これらに関連する事業者にとっては新たな事業機会となるはずです。
また、工場および生産設備の導入より生産量の増加が見込めると、その企業の販売量・販売額の増加が予想されます。販売量の増加は原材料の増加に繋がり原材料を扱う既存の事業者にとっては売上拡大が期待され、新規取引を望む事業者にとっては絶好のビジネスチャンスとなるかもしれません。
B 生産設備の設置や導入
新たな生産設備の設置や導入が進められると、その企業は生産量を増加させたり、品質・性能を強化させたりすることもできるので、売上高の増加が期待されます。また、生産の効率化が進められてコストが削減されれば、利益の改善も実現されやすくなるはずです。
生産設備を提供する事業者にとっては、当然ビジネスチャンスとなるはずです。既に設備の導入を進める企業との取引があり、設備の納入実績がある事業者にとっては受注が期待されるでしょう。しかし、納入実績のない事業者でも設備の導入計画を早めに掴み優れた設備の提案ができれば、採用候補として検討してもらえる可能性は十分にあります。
そのため生産設備の設置計画が有価証券報告書に乗る前の構想段階でその企業にアプローチすることが必要です。経営戦略の課題として生産設備の増強が示されている企業には迅速にアプローチし、具体的な計画段階からプロジェクトに参加していくことが求められます。
なお、有価証券報告書の【設備の状況】の箇所を確認すれば、現在の状況や計画案件の概要を掴むことは可能です。既に森永乳業の【設備の状況】の一部を紹介していますが、それら以外にもチーズ製造設備、デザート製造設備、チルドパック製造設備、乳原料製造設備が計画されています。
これらの設備については投資予定金額が示されているだけですが、既存の【主要な設備の状況】のデータからどのような投資になるかを予想することも不可能ではないでしょう。
| 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物および構築物 | 機械装置および運搬具 | 土地(㎡) | 工具器具備品 | リース資産 | 合計額 | ||||
| 多摩工場 | 食品事業 | 市乳・飲料・デザート製造設備 | 5,278 | 8,682 | 14,018 (107,920) | 130 | 258 | 28,369 | 246 |
| 神戸工場 | 食品事業 | 乳飲料・ヨーグルト・流動食製造設備 | 11,571 | 7,711 | 1,437 (16,424) | 98 | 16 | 20,837 | 158 |
*森永乳業グループ(当社および連結子会社)の主要設備に関する情報の一部抜粋
有価証券報告書には上表のようにグループ会社の設備に関する帳簿情報が記載されており、建物および構築物、機械装置および運搬具、工具器具備品やリース資産の価額が示されています。減価償却を考慮すれば、初期の投資額も予想できるので、これらを参考に現在の計画中の投資案件の内容を大まかに予想することもできるはずです。
C 営業拠点の建設・設置
自社ビル建設により営業拠点が設置されれば、建設工事関連や事務機器・什器関連の需要が期待できます。計画を進める企業にとっては営業力の強化に繋がるため売上高の増加も実現しやすくなるでしょう。
D 物流拠点の建設・設置
物流拠点が設置されれば、その建設工事関連や事務機器・什器関連の需要が期待できます。計画を進める企業にとっては物流網の拡充や効率化により物流サービスの向上とコストダウンが実現され収益の改善に繋がる可能性も低くありません。
E 研究開発拠点の建設・設置
研究開発拠点が設置されれば、その建設工事関連、研究設備・機器や事務機器・什器関連の需要が期待できます。計画を進める企業にとっては新技術や新製品の開発により企業の成長力の強化が実現されやすくなるはずです。
3-2 経営戦略の情報を投資に活かす
個人投資家などが企業の決算情報を投資の判断材料にすると、投資のリスクを軽減する効果などが得られ投資の失敗を防ぐのに役立つでしょう。
株式の銘柄を評価・選定するための方法はたくさんありますが、株価の過去の値動きの傾向から今後の値動きの傾向を予測するというテクニカル分析を重視して投資を行っている方は少なくありません。
テクニカル分析や経営指標・株価指標を使った分析も有効ですが、データだけに依存した投資はリスクを高めることもあります。使用されるデータは過去のものであり、将来を約束するものではありません。
そのため将来の動きを過去の数値としてのデータだけでなく、経営戦略や中期経営計画などの定性データも加えた判断をしないと投資判断を誤る可能性が高くなるのです。
たとえば、森永乳業の株価ですが、2014年度から15年度にかけて営業利益が大幅に落ち込み低迷した状態でしたが、その時の株価も1,500円から2,000円の間と芳しくありませんでした。
しかし、それらの時期から経営戦略の課題として生産の効率化等によるコスト削減が実施され16年度には14年度水準以上の営業利益が回復し17年度・18年度には最高益を更新しています。その結果、株価も16年度に3,000円を突破、17年度には4,000円、18年度には5,000円を突破した時期もあるのです。
この5年間の売上高は横ばいと良くありませんが、株価の上昇は利益のV字回復を市場が素直に好感した結果といえるでしょう。しかし、18年4月の半ばころより株価は4,000円台から徐々に下落し6月には3,000円台後半に落ち込んでいます。
前に紹介しましたが、同社の18年度の営業利益は6億円の増益を達成しましたが、+2.8%の増加と決して高い伸び率ではありません。19年度の経営戦略でも引き続きコスト対応力の強化が盛り込まれていますが、市場では今まで実現したような利益の伸び率は期待できないと判断した可能性が高いです。
営業利益額はこの5年間で大幅に改善したものの売上高は横ばいで、ほとんど事業規模は成長していないといえます。19年度の経営戦略の内容では成長に向けた取り組み内容も盛り込まれていますが、株価の上昇を期待させるほどの有望かつ具体的な内容は多く示されていません。
つまり、収益の大幅な上昇を見込める要素が不足しており、それが株価に反映されていると推察されます。ここ数年間に急激な上昇を見せてきた同社の株価ですが、収益の上昇が期待しにくくなれば今までの反動が出やすくなり、今はその兆候が出始めている可能性もあるでしょう。
このように投資の判断にあたってはテクニカル分析等に加えて経営戦略などの定性データや財務データによる分析も活用すれば、将来の株価予想もしやすくなるのではないでしょうか。
3-3 経営戦略の情報を就活に活かす
就職先を検討するための必要な情報は人によってさまざまですが、企業の成長・発展、進んでいく事業の方向性などで企業を評価したい場合には経営戦略の情報が役立ちます。
有価証券報告書の中には平均給与、平均年齢、平均勤続年数、従業員数などの情報が含まれており、その情報から企業の従業員の姿、輪郭をイメージすることもできるでしょう。
労働条件、福利厚生や求める人材像などについては企業のWEBサイトや会社案内などで確認する必要がありますが、企業の将来性・成長性、拡大する事業、などの経営に関する情報なら経営戦略の情報が役立ちます。
就職者・転職者が就職先を決める理由には、給与が高い、職場の雰囲気がよい、福利厚生が充実している、といった給与や職場環境の良さが大きな決め手になっています。ほかでは、仕事の内容が魅力的、将来性が高い、社会貢献できる、といった仕事や企業への期待などの理由が給与等の理由と同じくらい多くなっているのです。
この「仕事の内容が魅力的、将来性が高い、社会貢献できる」といった内容を会社案内などから確認することもできますが、決算説明会資料などの情報を見ることで自らがそれらの点を評価できます。
どの事業分野に力を入れているのか、何年後にその事業が中核事業になるのか、そして企業は成長・発展できそうか、などについて決算説明会資料を読み解けば自分で評価するのも困難ではないでしょう。
たとえば、先の森永乳業の経営戦略では、健康・栄養・機能性といった面での新商品の開発および販売が重要な課題となるので、これらの分野の業務に従事したい方には最適な就職先候補になるはずです。
生物科学分野などを専攻する学生や、他の会社に在籍する同分野の研究員および生産技術員などが就職先・転職先の候補として同社を検討する価値があるのではないでしょうか。
とくに研究開発分野の業務に従事したい方は、有価証券報告書の【研究開発活動】の項目の内容なども参考となるでしょう。ここでは研究方針、研究開発費、主な研究開発活動の内容が簡潔に記載されているので、従事したい仕事があるか、今後その仕事に就ける可能性が高いかなどの判断もできるかもしれません。
また、森永乳業は戦略項目の一つとして国際事業の強化を挙げているので、海外業務に就きたい、海外で仕事をしたい、海外業務での経験を活かしたい方などにとっても有望な就職先になる可能性があります。
同社の国際事業は、インドネシアやパキスタンなどで育児用ミルクの市場拡大を実現し、米国ではアロエ葉肉入りヨーグルトの先駆者として米国内市場のけん引役を果たしています。
19年度も戦略課題として国際事業での利益の改善や事業の拡大が計画されていることから海外で活躍したい方にとっては、森永乳業は最適な就職先候補になるでしょう。
このように決算資料は就職・転職を検討する上での企業情報が多く含まれているので、就職希望者等には欠かせない判断材料になるはずです。