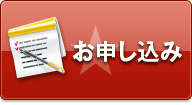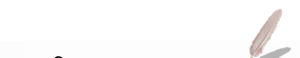3年連続でノーベル賞を受賞するなど、日本の科学力が世界で高く評価されているのはとても喜ばしいことと言えます。
しかし、日本の科学者や技術者が恵まれた環境で仕事ができているかどうかについてしばしば議論になります。
2014年にノーベル物理学賞を受賞した中村修二教授が起こした青色LED訴訟はとても有名です。在籍していた会社との間で発明対価について争われ、約8億円で和解に至りました。
この訴訟をきっかけに会社の発明はだれのものか、相応の対価はいくらになるのかについて国内で議論が活発に交わされるようになり、2015年、特許法の改正が行われました。
目次
1 社員の発明は企業のものとすることができる

これまで職務上の発明の特許権は社員のものとされていましたが、前述の特許訴訟など巨額の支払いを求める裁判が相次いだことを受け、特許法の改正が2015年に行われました。
改正法では、あらかじめ特許を受ける権利を社員から企業に変更できるようになりました。社内の規定で、「職務上の発明は会社に帰属する」と明記すれば、職務発明の特許を受ける権利は会社にあり、社員から会社への譲渡手続きは不要です。
しかし、こうした社内規定や契約がない場合、職務発明の特許を受ける権利は発明者(=社員)に帰属します。
2 発明者には相応の対価を支払うことが条件

改正法では、発明者(=従業員)保護の観点から「従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する」(特許法35条4項)と規定しました。
つまり、会社はあらかじめ特許を取得させる権利を会社に帰属させる場合、発明者である従業員に相当の対価を支払うことを約束しなければなりません。
前述の中村修二教授が、勤めていた会社から相応の対価をほとんど貰っていないことがニュースに取り上げられた際、「日本は社員を奴隷のように扱っている」と国際社会から批判を浴びました。
今回の改正により、特許権の取り扱いについて社員が萎縮せずに、発明に専念することができるのではないかと期待が寄せられています。

3 国際競争力強化のため特許料を引き下げ
さらに、中国をはじめとする海外企業が日本の企業より先に特許を取得し、市場を占有するケースが増えてきたことを受け、改正法では、特許取得の費用を引き下げました。
10%程度取得にかかる費用を引き下げ、日本企業による特許取得を後押しします。